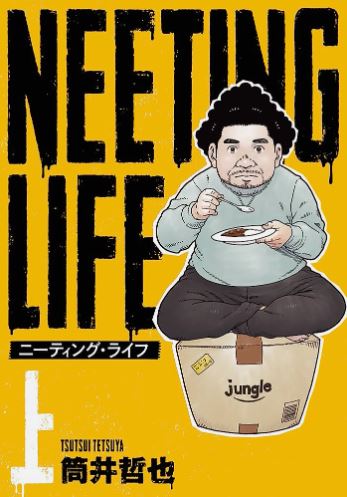アメリカ/カナダ/フランス 2021
監督、脚本 シアン・ヘダー

聾者の家族の中でたった1人の健常者である女子高生が、歌うことに類まれなる才能を発揮し、卒業後の進路にあれこれ悩む家族ドラマ。
さて、末っ子の女子高生であるルビー、なんで進路に悩んでいるのかというと、常日頃から家族の通訳として手話を駆使し、世間とのパイプ役を幼い頃から務めてきたから、なんですね。
オヤジと兄貴は漁師なんですけど、ルビーがいないと漁協とのやり取りもできなければ卸値の交渉もスムーズにできない。
本人たちはできてるつもりでも、周りは「どうせ聞こえてないし」とハナから舐めてかかってる部分がある。
相互依存というと語弊があるし、言い過ぎですが、家族が収入を得て円滑に社会生活を営むための必要不可欠なピースなんですね、ルビー。
そんな立場にいる女の子が天才シンガーだったなんて、あまりにも皮肉すぎる運命のめぐり合わせじゃねえかよ!って話で。
まあ、ちょっと狙いすぎというか、漫画的すぎるな、と思わなくもないんですけどね、歌自体がどんなものか理解できない聾者に、音楽の素晴らしさを解こうとする試みは高く評価していいと思います。
これは冒険だったと思うし、勇気のいることだと思うんで。
正直ね、私はそんなの無理だと思ってる方なんですよ。
詳しくは書きませんが聾者がどういうものであるか、私はよく知ってるつもり。
なのでルビーの親父がラップはリズムが気持ちいい、と言ってるのもよくわかるし、聾者がいかに疎外感を感じているかもすごく理解できる。
音楽の三要素って、リズムとメロディとハモーニーですから。
そこからメロディとハーモニーを除外した状態で音楽がなんであるか、わかろうはずもない。
つまりこの作品は、絶対的不理解に、いかにして理解(譲歩?)を引き出すかを裏テーマにしているといってもいい。
いや、悪いけどありきたりな家族愛とやらで片付けられても私は酷評するだけだよ、と最初は斜に構えてたんですよ。
どうせ魂で伝えるんだとか(そういうセリフも実際にあった)その手の曖昧に都合の良い感情論でごまかんすんでしょ?と思ってたら、違ってて。
あ、これは嘘ついてない、と最初に思ったのはコンサートのシーン。
突然、場面が無音になるんです。
あたりを不安げに見回す親父の姿。
彼の視界に飛び込んでくるのは大きく手拍子を打つ人たちや、目頭をハンカチで押さえる老女のアップ。
親父は彼女の歌が、人々に何をもたらすのか、視界を通じて脳内に変換するんです。
白眉は車の荷台でルビーが親父1人のために歌を歌うシーン。
はたして親父は娘の歌を理解するために何をやったか?
もうね、号泣ですよ。
お互いがね、お互いのためにわかりあおうと一生懸命なんですよ。
くっそ、こんな場面を用意してやがったのか!とズルズル鼻水垂れ流し状態。
完全にしてやられましたね。
また、聾者の家族の日常を、不必要に暗く描いてないのも素晴らしかった。
社会にちゃんと受け入れられてるとは言い難い状況で、卑屈になってしまうようなこともきっとたくさんあるはずなのに、みんなナチュラルに明るいんです。
なんならむしろ笑わせてくれたりもする。
ぶっ壊れた家庭に暮らすルビーの彼氏の存在が、我々は障害をどう受け止めるべきなのか?を考える試金石にもなっていて。
どうしても理解できないことは確かにあるかもしれない、それでも認めあう(わかりあう)ことはきっとできるはずなんだ、という前向きな強いメッセージが物語から伝わってきましたね。
そりゃアカデミー3部門受賞するわ、と納得の力作でした。
ちなみにオリジナルは2014年に発表されたフランスのエール!という作品らしいんですけど、リメイクでここまでやれれば上等だと思いますね。
たいていハリウッドリメイクの感動作って、肝心な点が抜け落ちてたり、余計な脚色があったりするものだからさ。
オリジナルは見てませんが、きちんと成立してる、と私は思った。
とても優しい映画だと思います、見て損はなし。