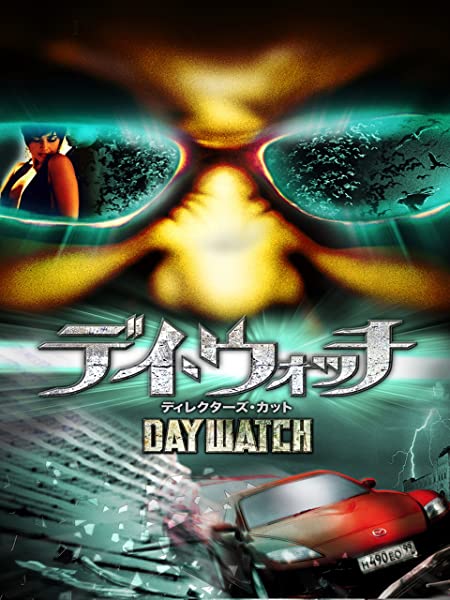アメリカ 2013
監督、脚本 コーエン兄弟

実在したミュージシャン、デイヴ・ヴァン・ロンクをモデルに、60年代ニューヨークに生きた売れないフォークシンガーを描いた一作。
さて、モデルであるデイヴ・ヴァン・ロンクですが、私は名前すら知らない有様でして。
もともと海外のフォークには明るくない、ってのもあるんですが、調べてみたところによるとデイヴ、なんとアルバム21枚も出してて当時のフォークシーンにおける顔とも言える存在だったとか。
若い頃はジャズバンドで演奏し、一人で歌うようになってからは複雑なコード進行を駆使したフィンガー奏法が特徴的なプレイヤーとしてリスペクトされていたとのこと。
いやいやいや映画と全然違うじゃないすか!
複雑なコード進行の楽曲なんて主人公のルーウィン、やってねえし。
しかもルーウィン、アルバムを発表したはいいが、まるで知名度は高まらず、誰からも支持されてないろくでなしだし。
デイヴ・ヴァン・ロンクに詳しくないんで、実は彼にもそんな時代があったのかもしれませんが、映画を見た限りではデイヴの逸話をいくつか拝借して全くのオリジナルに仕上げた印象が濃いですね。
いうなればルーウィンは、あの頃のニューヨークシーンの底辺でうごめいていた有象無象の貧乏ミュージシャンの総体、と考えて見たほうがスッキリ内容に入っていける気がします。
しかしまあなんというか、いちいち「わかる!」といいたくなる映画でしたね、これ、私にとっては。
ルーウィン、技術はあるんです。
それは周りからも認められてる。
けれど自分がやりたいこと、表現したいことに確固たるイメージがあるから、妥協を許さないし、他者のプレイするつまらない音楽を許容できない。
挙げ句にライヴハウスで口汚い野次を飛ばしたりする始末。
ちょっとした生活費を稼げそうな仕事も「コーラスとかやりたくない」ってな理由で断って、意固地なまでに自分の音楽だけを守ろうとする。
結果、住むところもなければ、安定した収入もなく、プレイできる決まった場所もなければ、熱心な支持者もいない。
それでいて女にはだらしなく、プライドだけは一人前以上、ときた。
これ、若い頃の俺じゃねえかよ!などと、少し思ったりなんかもして。
いや、私は女にだらしなかったりはしないですけどね、うん、そこはもう断固として主張しますけど。
ま、そりゃ、どうでもいいんですけど。
で、コーエン兄弟、そんなどうしょうもないルーウィンを悲観的になりすぎず、さりとて美化するわけでもなく、絶妙なさじ加減でどこかコミカルに描いていくんですね。
ろくでもなさ、救われなさを「踏みはずちゃってるおかしさ」でふんわりくるんでみました、みたいな。
もう、熟練の技ですよね。
多分、門外漢が見てもクスッとくるだろうなあ、と思えるシーンの連続だったりしますし。
かき回し役として猫を使う、ってのもさすがの一言でしたし。
で、私が一番感心したのは、この作品をありきたりなサクセスストーリーにしなかったことですね、やはり。
少々歌がうまかろうが、ギターが上手だろうが、クズはクズ、と監督は冷静に俯瞰してる。
けど、こんな風にあがいてる連中がいっぱい居たから、60年代のシーンは変革期として熱かったし、何かが起こりそうな気配だけはすごくあったんだよね、ってのがリアルに伝わってくる仕上がりになってる。
音楽シーンにおける時代の断面を切り取った秀作だと思いますね。
長年バンドにうつつをぬかしてた私が見て、全く違和感がなかったのは確かです。
あと、オスカー・アイザックは主演を務めるにあたってすごく研鑽を積んでるなあ、と思いました。
歌とギターを練習するのは当たり前として、ステージでの佇まいがね、見事にミュージシャンなんですよね。
そこはもう近年見たブルーに生まれついて(2015)のイーサン・ホークとタメを張るレベル。
ニッチな音楽もの、みたいな先入観を捨てて見て欲しい一作ですね。
わかりやすいハッピーエンドは待ち受けてないですけど、思いのほか誰が見ても楽しめる一作なんじゃないか、という気がしてます。