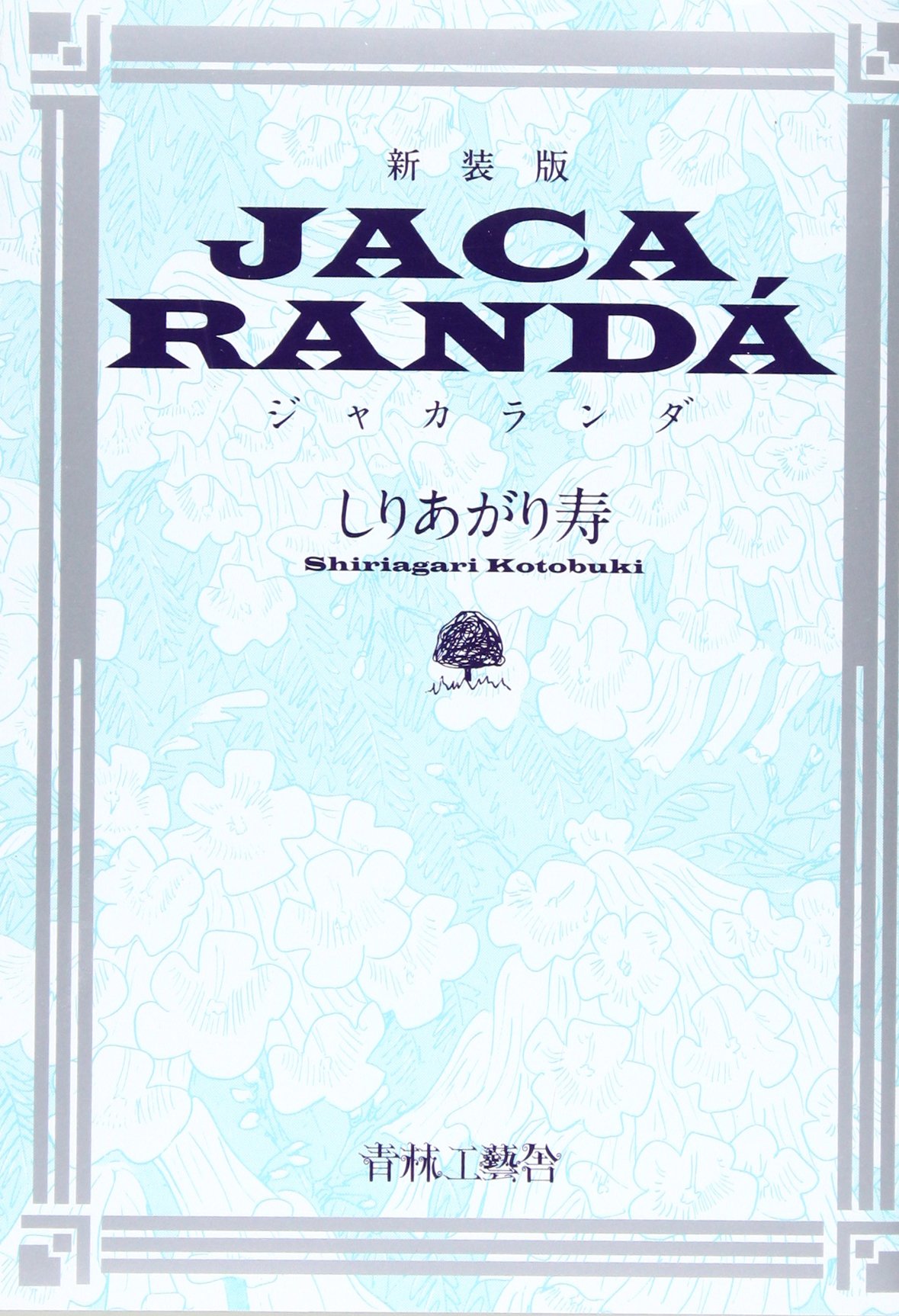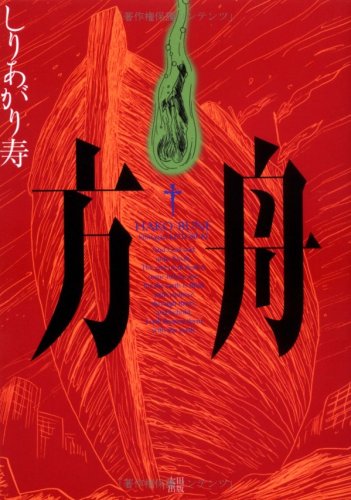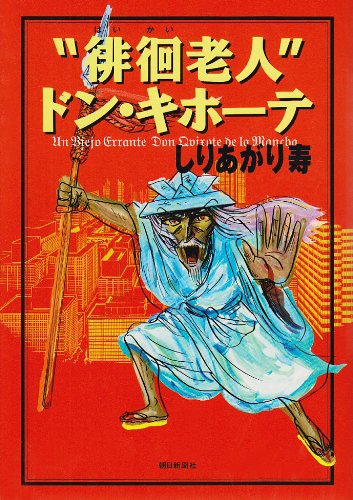2002年初出 しりあがり寿
青林工藝舎
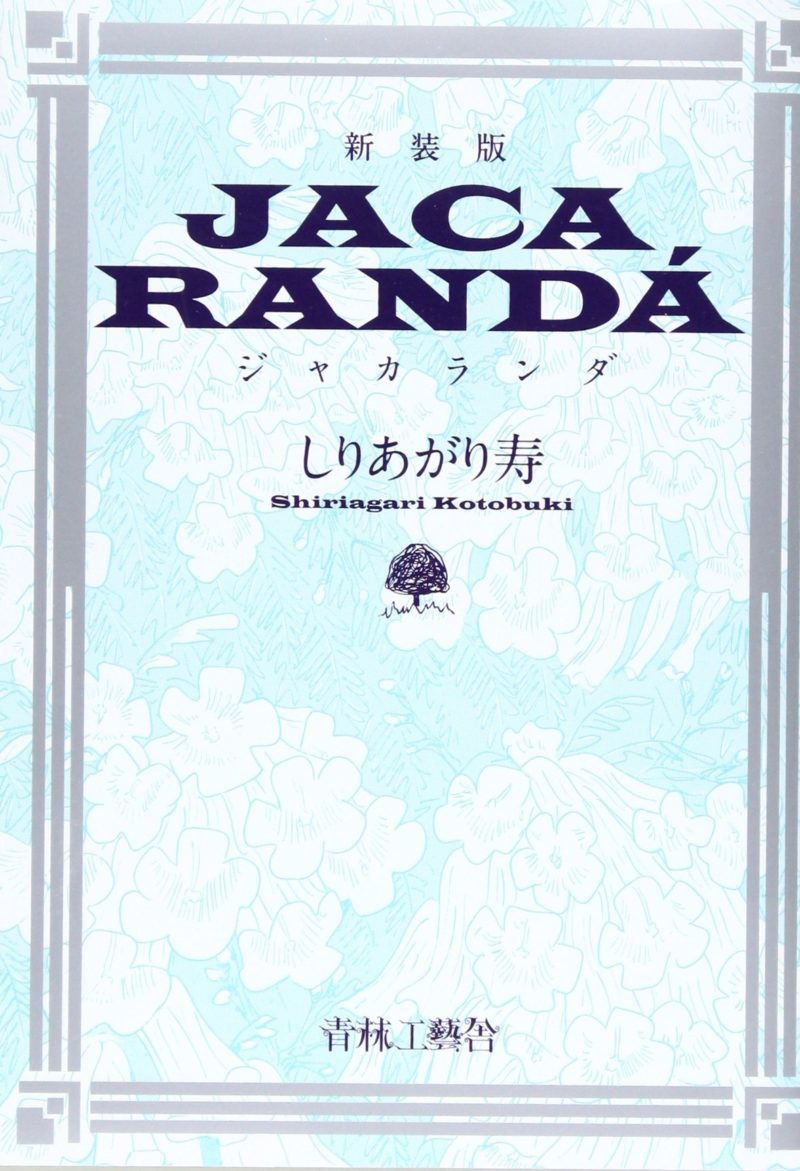
やってることは方舟(1999~)とほぼ同じというか、抗いようのない超自然なカタストロフを今回もテーマにしてるわけですが、作者の位置づけ的には方舟と対になる物語、のようです。
どこかでそんなことを語っていたような。
調べたけどソースが見つかんないんで自信はないです。
ある日突然、都心部に芽をだした、怪物的な大きさの巨木がもたらすライフラインの破壊を描いた作品なんですけど、私が「こりゃだめだ」と思ったのは未曾有の災害に右往左往する人々のドラマが一切描かれてないこと。
なすすべもなく唐突な死を迎える人たちを、ただただひたすらに延々と描き綴ってるんですよね。
言うなれば、スプラッターホラーにおける惨殺シーンだけで一本の映画を作り上げてしまった感じ。
誰得なんだよ、って話ですよ。
ページをめくれどもめくれども、ガス爆発や家屋倒壊で死んでいく人たちの阿鼻叫喚が途切れることなくこだましてるんです。
もうね、単純にしんどい。
それはもうわかったから、次の展開を、と渇望するも、ようやくその兆しが見えてくるのはおよそ250ページもの膨大な分量を消化してから。
あえて主人公を設定せず、ドラマ不在でドキュメンタリー風なのは、なんらかの意図が隠されているに違いないんでしょうけど、私はそれを探る以前に「つまらない」と思ってしまったものだから、考えを巡らせる気にもならなくてですね。
ま、寓話といえば寓話なんでしょうね。
巨木信仰の発生する瞬間みたいなのをラストで描いてるんで、現代における神話の創出を試みたのかもしれませんが、物語から与えられた情報量が少なすぎてなんとも判断がつかず。
単純に自然が都市をぶっ壊す話が描きたかっただけ、なのかもしれません。
衝動任せなのだとしたら、いかにもアックス掲載作品だよなあ、と思ったりもします。
作家の好きなようにやらせておくと駄目、の典型例なような気もしますね。
同じ破滅を描いた方舟では、驚くほどたくさんのものが伝わってきたのに、本書の低調ぶりはいったいなんだろう、と思いますね。
どうせなら「これが世界樹ユグドラシルの誕生である」等、ハッタリのひとつやふたつぐらいかましておけばよかったのに、と思ったりもするんですが、多分そういうことはやりたくなかったんでしょうね。
憤ってるのはわかるんですが、それと物語の作法は別、といったところでしょうか。