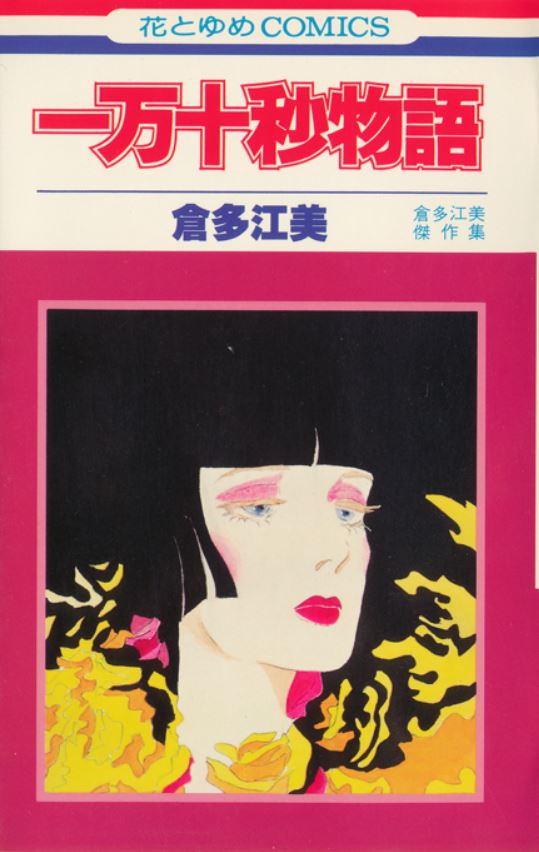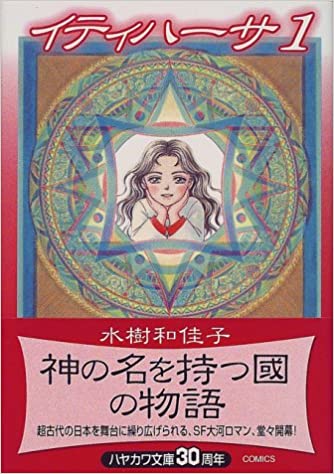1979~85年初出 水樹和佳子
ハヤカワ文庫
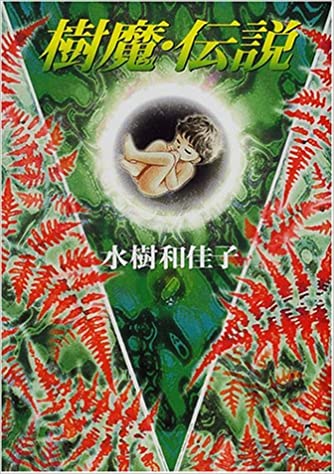
星雲賞を受賞するだけのことはあると納得できる内容ではありますね。
流星群に襲われて壊滅的な打撃を受けた後、なんとか復興をはたした西暦2505年の地球が舞台。
旧時代の世界とは政治の在り方も科学の在り方も違う未来の地球で、新たな災厄と再生を描いた「樹魔」も、進化を問うた「伝説」も、緻密に編み上げられたプロットとドラマチシズムが見事結実した名編と言えるように思います。
SFとして申し分なし。
特に「伝説」の時空を超えたラブロマンスは多くの人の胸をうったことと思う。
しかしだ。
しかしながら残念なことに個人的には、水樹和佳子の作家性みたいな部分でどうしてものめり込めない、無条件で大絶賛できない感覚がくすぶっていたりもする。
やはりこの2編って、萩尾望都を代表する24年組の作り上げた女流SFの流れを汲む作品だと思うんです。
あまりにも偉大すぎる先達に影響を受けるのは仕方がないと思うし、あんな作品を描いてみたいと言う気持ちも分かるんですが、やっぱりね、そこに作者なりの表現なり独自性が欲しかった。
SFマンガとして高い完成度を誇ることは否定しませんが、水樹和佳子のアイデンティティはどこに、と言う感じ。
イティハーサを読んだときの感想と同じことをまた書いてますけどね、私。
健全さにひっかかってるのかもしれません。
物語の壮大さに反して登場人物の誰もがあまりにも真っ当すぎるように私には感じられたり。
まあ結局これって「少女漫画の作法」を損なわない創作である、と言うことなのかも知れませんけどね。
なんせ80年代の作品なので、リアルタイムで読んでいない分、辛い論評になってしまっているかもしれないですが、世代を同じくする他の女流漫画家の作品と比較するとどうしても順当であるが故の既視感は否めない。
併録されている「ケシの咲く惑星」「月子の不思議」は近年の絵柄に近い85年の作品なんですが、樹魔」「伝説」ほどのインパクトはなし。
ここでまた私は作者が作者らしさを確立する過程でなにかを落っことしてきちゃったのかな、と邪推したりする。
ファンの方すいません。
表題作の素晴らしさがわからないわけではないんですが、どうも私にとって水樹和佳子は琴線にふれない漫画家のようです。