下苅り半次郎
1974年初出 スタジオシップ全7巻

跡継ぎに恵まれぬ将軍家綱の命により、御仏の子宮をもつ女を捜す諸国行脚へと身をやつした伊賀者番頭、堤半次郎の苦難の日々を描いた時代劇。
しかしまあなんとも凄いアイデイアだなあ、と感心しました。
ほんとこういうプロットって小池一夫ならではだと思います。
将軍直々のご下命ゆえ、ばかげた任務と納得の上で見知らぬ女の股ぐらを覗きこまねばならない半次郎の悲哀は、まさに封建主義社会のいびつさを描いた時代劇の真骨頂。
見つからぬことは承知のうえで野で果てる覚悟ながら、任務は決しておろそかにしない伊賀忍者の生き様は、悲運ゆえ胸をうちます。
このまま御仏の子宮を探す旅を何らかの形でしめくくってくれれば思わぬ傑作になったのでは、と思うのですが、残念だったのは、途中で何故か家綱が急逝して将軍が代替わりし、ストーリーに若干の修正がほどこされてしまったこと。
3巻ぐらいから意地悪な5代将軍綱吉と無理難題をなんとか工夫と知恵で乗り切っていく半次郎の主従関係の物語になっちゃうんですね。
もはや下苅りも御仏の子宮も関係なし。
作者初期の忍者もの鬼輪番みたいな展開に。
結局下苅りネタだけでは続かなかった、という事なんでしょうかね。
当時は映画化もされた人気作だったようですが、本編は途中で打ち切られたかのように未完。
なんとも評価が難しいです。
最初はインパクトがあったんですが、なんとなくしぼんでしまった、ってのが正直なところでしょうか。
青春の尻尾
1975年初出 小学館全6巻

まだ世に出る前の若かりし諸葛孔明を描いた中国歴史ドラマ。
お、小池版プレ三国志か、と色めきたつ人も中にはいるかもしれませんが、実態は三国志どころか史実にすらかすりもしていないのでは?と思われる独創性たっぷりの伝奇ファンタジーなんで、そこはやや注意が必要かもしれません。
なんせいきなり仙人が登場したかと思えば、幽明界の桃を食べて選ばれた人間となり、挙句に鬼界を支配する四姉妹を従えたりと、荒唐無稽をものともせずやりたい放題。
物語は戦乱の火のやまぬ中国を放浪する孔明が、鬼界の四姉妹の力を借りて問題を解決していく方向で進んでいくんですが、これは立身出世伝なのか、それとも単に強大な力を手に入れた若者の人間ドラマなのかという点で各話にブレがあり、なんだか舳先が定まらない、というのはあったように思います。
漠然と世のため人のためにつくしたい、と孔明に語られてもですね、ストーリーの行き着く先が見えてこないし、三国志にリンクしそうにも思えなくてですね。
四姉妹に願いを遂行させるためには性交する必要がある、などというルールを定めたのもいささか足枷になっていたような気もします。
まあ、読者サービスなんでしょうけど。
無力な若者が四姉妹を妻と呼び、その力の恩恵にあずかりつつも人との係わり合いについて考える、という構造だけを抽出するなら、 後の「魔物語愛しのベティ」とほぼ同じだな、と思ったりもしました。
結局、魔物語に至るためのたたき台となった作品なのかもしれません。
まだこれから、というところで突然終わってるので、おそらく人気が出ず打ち切りになったのでは、と思われます。
諸葛孔明でこんなことが出来るのは小池一夫だけだと思うんで、そういう意味では楽しめたんですが、 ちょっと自由奔放にやりすぎた、ってなところでしょうか。
どちらかというとファン向け、ですかね。
少年の町ZF
1976年初出 小学館全9巻
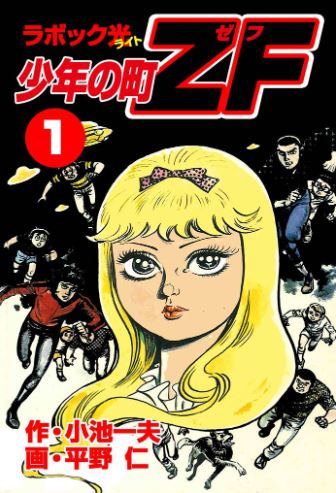
突如宇宙より飛来した侵略者に、たった10人で立ち向かうことになった少年達を描いたサバイバルSF。
侵略SFの名画「ボディスナッチャー恐怖の街」をご存知の方は、そちらを思い出していただけると話は早いかと。
全人類が宇宙人に憑依され、人格を失った状況下で、ちょっとした偶然からその支配を免れた少年達はいかにして宇宙人に対抗していくのか?が物語の大筋なわけですが、 まあ前半はそれなりにスリルもあって楽しめなくはなかったんです。
小池一夫が本格的にSFをやる、ってのも珍しいですしね。
実際、色んな引き出しからあらゆる知識を総動員させてもっともらしさを構築しようとする手管は決して悪くはなかった、と思います。
一体侵略者はどういう生命体なのか、その目的はなんなのかを解き明かしていくくだりに、いかにもSFらしい知的興奮があったことは確か。
問題はそんなSFにすら、いかにも作者らしいマッチョイズムやら愛やらを持ち込んだことでしょうか。
いやね、宇宙人の使者である女を味方に引き込むのはいいんですが、それを無理矢理レイプして妻にする、って、もう滅茶苦茶だと思うんですよ。
そもそもその使者がどういう生命体であるかもわからないのに地球の価値感を押し付けて、俺はこの女と生涯を共にするっ!て、愛を叫ばれてもですね、正気か、という話であって。
自分の得意なテリトリーに物語を引き込もうとするのはかまわないんですが、それが侵略SFというジャンルにそぐうものなのかどうか、そのあたりの検証がごっそり抜け落ちてるんですよね。
だからどう外堀をそれらしく固めても、結局物語の図式は10人の男達VS強大な権力者、みたいな構図になる。
この内容だと、別に敵は外宇宙からの侵略者でなくたって全然問題ないわけです。
その証左にエンディングでは宇宙人が、ある事に心うたれて地球を去る、という結末が描かれてます。
なんじゃこりゃ時代劇かよ!って。
とても高校生以下とは思えない、主人公達の大人びた言動の数々もよろしくない。
子供達ならではの危うさ、純粋さがあってこそのタイトル「少年の町」だったと思うんですね。
これじゃあほとんど「アダルトの町」。
漂流教室にも成り得た可能性のあった作品だと思うんですが、どこかで舵取りを間違えてそのまま修正がきかなくなってしまった印象。
怪作です。
小池一夫はSFに向いてない、とつくづく思った次第。
春が来た
1976年初出 双葉社全8巻

大奥お庭番として50年以上にわたって禁欲生活を送り続けてきた忍者と、町方十手ものとして妻も娶らず職務にいそしんできた二人の、退役後の人生を描いた時代劇。
当時にしては相当斬新なストーリーだった、と思います。
なんせ主人公の二人が齢60を数えようか、というジジイなんですから。
人並みの生活を送ることも叶わず、ただ実直に職責を担い続けた老人達が、老後に人生を取り戻すことができるか?が作品のテーマなわけですが、恐るべきは未曾有の高齢化社会を迎えた現在日本の抱える問題と内容が微妙にリンクしている点でしょうね。
まさか予見していた、なんてことはないと思いますが、時代は違えど今だからこそ興味深く読める部分は過分に内包しているように私は思います。
少なくとも「老後の生」をどう生きるか、のヒントにはなると思う。
もちろん小池劇画ですんで、誰もがこうあってほしい、こうありたい、と思う姿をドラマチックに、ケレン味たっぷりに、具現化しているのは確かで、こう都合よくはいかないだろう、というつっこみもきっとあることでしょう。
でも希望をもてそうな気にはなると思うんです。
そのことだけでこの奇抜なプロットの作品は後世に伝えられる価値はあると思う。
きちんと完結していないのが残念ですが、私は読んでいて、こんなクソジジイになりたい、と思いましたね。
若干コメディ調なのもこのコンビの従来の路線を上手に裏切ってる、と感じました。
あまり話題にのぼらないシリーズですが、私は好きですね。
修羅雪姫
1976年初出 スタジオシップ全3巻
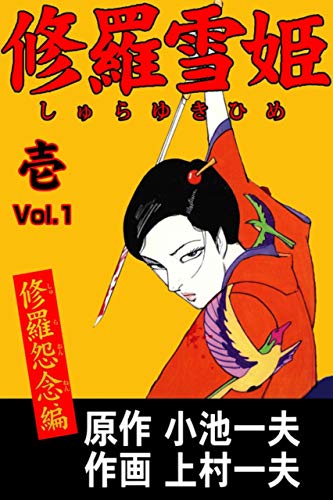
明治時代を舞台に、殺された両親の恨みを晴らすために仇探しの旅を続ける主人公雪の、血で血を洗う日々を描いた復讐譚。
かのタランティーノの「キルビル」は本作を模倣している、と小池一夫が訴えたところ版権料が支払われた、という話が有名ですが、まあ、私の実感としてそれほど酷似している、とも思えません。
キルビル自体が色んな物語のオマージュですし。
キルビルからこの作品に興味を持った人も今となっては多いかと思いますが、あんまり意識しない方がいいような気もします。
あれはあれ、これはこれ。
やってることはI・餓男ボーイぐらいから何度となく繰り返されている小池劇画お得意のパターン。
今回、少し毛色が違うのは、主人公が女であることと、明治時代であること。
作画が昭和の絵師と呼ばれた上村一夫であることも作品に独特の艶っぽさを加味している、といっていいでしょう。
小池作品に慣れ親しんだ身としてはそれほど目新しさを感じたわけでもないんですが、和服の妙齢の女性が単身長ドスを仕込んで荒くれどもに切り込んでいく、という画が問答無用でかっこいい、というのはありますね。
ただただ亡き両親のために、その怨念を晴らすため、血しぶきをあびながら「涙はとうに捨てました、心はとうに棄てました」なんて独白されると、どうしたって心揺さぶられるわけです。
雪が小池劇画の登場人物のなかでも出色のキャラであることは間違いないでしょう。
あっけなく終わっちゃったような印象もあるんですが、私の中では女囚さそりと並んで70年代屈指のアンチヒロインではありますね。
不思議な磁力がある作品です。
小池×上村の思わぬ化学反応の賜物、と言えるかも知れません。
実験人形ダミーオスカー
1977年初出 スタジオシップ全19巻

人間と寸分違わぬ等身大人形を作る天才人形師、渡胸俊介の奇矯な放浪の日々を描いたアダルトなアンチヒーローもの。
この作品が独特なのは主人公渡胸俊介が、オスカーと呼ばれる別人格を心に巣食わせた2重人格者である点でしょうね。
悪魔のごとき技術を持つが、普段はチビで気弱な冴えない人形オタなんです。
それがなにかのきっかけでスイッチがはいると、突然自分を超人間などと言い出し、肉体は筋骨隆々になるわ、やたら頭が切れるわ弁はたつわ、短小がありえない巨根になるわ、と見違える変貌を遂げる。
オスカーが表に現れて居る時にはFBIでも手をこまねく事件を自らの主導で、人形を使って解決したりするので、IQや洞察力、判断力すら飛躍的に上昇する、と考えていいように思います。
ああこれは結局のところ、男性読者諸氏の変身願望を満たす作品なんだろうな、と思ったりもしました。
小池現代劇画ではよくあるパターン、女性からのもてっぷりも半端じゃないです。
次から次へとなで斬りです。
マッチョイズムの極みというか男根崇拝というか、いったん情交をかわしたら全部の女性キャラが「こんなの初めて」って、言いなりになるんだから、途中でちょっと阿呆らしくもなってくるほど。
男性向けグラビア誌GOROに連載された作品ですんで、きっちりニーズに答えた、ということなんだろうなあ、とは思いますが。
私がこれは凄いな、と思ったのは叶精作の精緻な作画ですね。
特に女性の絵に関してはこの時代、右に出る描き手はいなかったのでは、と思えるほどなまめかしく色っぽい。
下着やガーターベルトのレースまで丁寧に描かれてるのには本当に感心しました。
ストーリーそのものは巻を重ねるにつれ「オスカー色まみれ大活躍譚」みたいな方向にどんどん進んで、天才人形師の何を描きたかったのか、2重人格者としての心の葛藤はどう始末をつけるのか、みたいな部分が置き去りなまま、なんとなく過去を回想して中途半端な状態で14巻にて一端終わります。
別紙にて再開された後も大きく路線は変わらず、最後は家庭にその帰着を求めてこじんまりまとまっちゃうんですが、やっぱり欲を言えば2つの人格が融合するその先を見たかった、というのはありますね。
そういう方向性に中盤いきかけたんですけどね、なんとなく軌道修正されてしまった。
人形師と言う存在が、現在社会の中でどう機能するのか?というオチもこれではあまりに儚いし、仕事として成立するようにも思えない。
設定や素材はとても興味深かったんですが、作品を貫くテーマがあいまいだった、といったところでしょうか。
アダルト版超人ハルクみたいなもんだ、と思って読むのが正解かも。
それはそれでまたちょっと違うか。
夜叉神峠
1977年初出 少年画報社全4巻
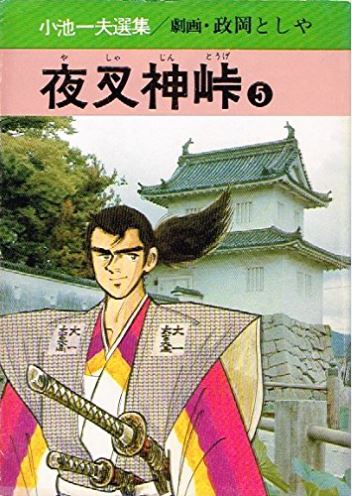
刀ひとつ満足に振ることもできない非力な下男が、師を得て大きく変貌を遂げていく様子を描いた時代劇。
いわゆる立身出世ものと捉えるのがわかりやすいかと思いますが、物語の序盤で、主人公がとある人物の血縁者と判明することから、ゴールが見えにくい、ないしは実現可能とは思えない到達点を掲げてるように感じられて、素直にストーリーに入り込めないというのはありますね。
どう考えたって単身で実現できるような夢じゃないですし。
いくら有能でも下男あがりの無学な男がそこまで上り詰めるってのは、相当な幸運に恵まれてなきゃ無理、と思いますし。
というか私は、自死すらも厭わぬほど思い詰めた主人公が、貧弱な肉体でも戦える剣法を身につけて独り立ちしていく物語だと思ってたんですよ。
それこそ上がってなンボ!の太一みたいに。
そもそもが危ういわけですから。
本来なら武士としてやっていける体力も体躯も併せ持ってないわけですし。
それが胎息の剣(剣技)を身に着けた途端、いきなり賢者、達人ですら到底成し遂げられぬだいそれた夢を語りだすんです。
周りの環境に憤った、師に後押しされた部分もあるんでしょうけど、もう人格変わっちゃってるんですよ。
1巻の主人公はいったいどこへ?って感じ。
中盤の展開なんて、もはや極悪非道とすら言っていいでしょうね。
こんな身勝手なやつ、見たことないわってなレベルで女が犠牲になっていく。
とにかく主人公のキャラクターが定まらない、というのが全編を通して言えていて。
終盤なんか公儀御庭番の頭領や甲賀忍者軍団のNO2とサシで駆け引きしたりしてますから。
いつの間にそこまで機転の効く胆力の座った男になったんだ、と。
エンディングがまた都合が良くてねえ。
お前に今更そんな幸せを求める権利なんざない!とマジで思った。
これまでの所業を顧みるなら、すぐさま頭丸めて坊主にでもなれ、と。
色んなアイディアをぎゅっと詰め込んだ意欲作だとは思いますが、とかく迷走気味というのが正直な感想でしょうか。
まあ風呂敷の広げ方が小池一夫らしいといえばらしいんですけどね。
半蔵の門
1978年初出 スタジオシップ全19巻
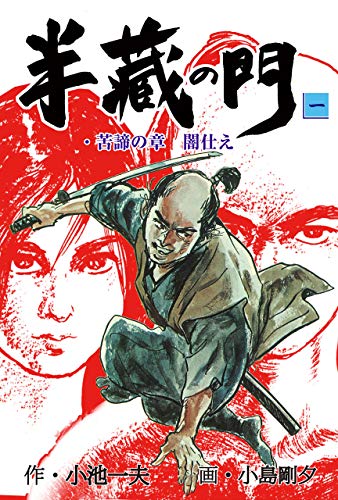
小池版、徳川家康。
タイトルにある半蔵とはもちろん服部半蔵のことで、言わずと知れた伊賀忍者の大首領。
家康と半蔵の主従を越えた信頼関係を物語の軸に、波乱の戦国時代を描いた作品。
ああ、小池一夫もこういう原作を書くんだなあ、というのが私にとっては意外でしたね。
実在の歴史上の人物を配し、大きく史実を捻じ曲げずにストーリーは進んでいくんです。
そこに拝一刀も唇役腕下主水も登場してこない。
史実をベースに、ケレン味たっぷりに、オリジナルキャラで滅茶苦茶やるのが流儀か、と思ってましたんで、この真っ当さは幾分拍子抜けではありました。
もちろん登場人物の関係性や性格設定は大きく改変されている、と思います。
そもそも半蔵と家康がこうも濃密に心を通わせあった間柄であったはずがない。
読みどころはそのあたりでしょうね。
小池氏は戦国時代における家康や武将たちをどのように分析していたのか、その独自解釈が実に興味深いのは確かです。
週刊現代に連載されていたことが作風を従来より控え目にさせていたのかもしれません。
私が読んでいて一番おもしろかったのは、終盤、半蔵が武田信玄を単身暗殺するために、ジジイに化けきって、素っ破の女首領とねんごろになってしまう展開ですね。
こんな突飛な話を真実味たっぷりにもっともらしく描けるのはこのコンビ以外にありえないと思う。
残念なのは信長惨殺、家康天下統一のくだりが駆け足で終わってしまったこと。
このペースで描いてたらとても天下統一まで19巻では無理だぞ、と思ってたら案の定。
人気の問題なのか、他の要因があったのかわかりません。
特に本能寺の変はどう描かれるのか、楽しみにしていただけに残念。
尻すぼみな印象はぬぐえませんが、一風変わった戦国絵巻として独特なポジションにはあると思います。
個人的にはもっと半蔵目線で物語が語られても良かったのでは、と思ったりもしますけどね。
多羅尾伴内
1977年初出 講談社全5巻
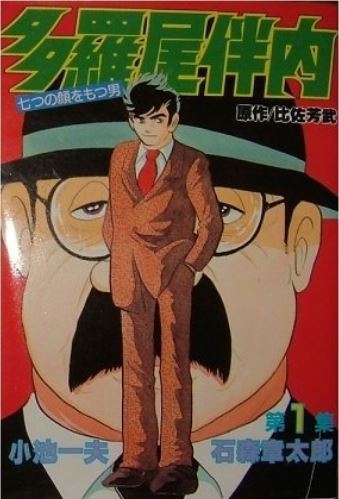
1946~1960年の間に片岡千恵蔵主演で11作品が公開され、大人気を博した映画シリーズの漫画化作品。
とはいえ、漫画では二代目多羅尾伴内が主役を張っており、正確に言うなら映画の続編を意図した、というべきか。
しかしすごい顔合わせだなあ、と思いますね。
小池一夫と石ノ森章太郎って・・。
両作家とも作風が確立した描き手(書き手)だと思うんですが、メディアミックスとはいえ、個性がぶつかり合わなかったのだろうか、と。
特に小池一夫は原作を必要としない漫画家と組んだことって、ほぼなかったと思うんですよ。
石ノ森章太郎も平井和正を除外すれば同様。
お互い、妥協点を探りながら連載を進めていったのかなあ、などと思いながらページをめくっていったんですが、うーん、これ、噛み合ってないですね、やはり。
多分、石ノ森章太郎は小池一夫の原作通りに漫画描いてない、と思う。
らしさをふりまきつつも、最終的には自分の流儀で各話を締めくくってる気がする。
で、それがどっちつかずの中途半端さ、しいていうなら煮えきらなさを感じさせる羽目に。
ま、題材そのものが古すぎる、というのも実際問題としてはあります。
だってね、知らないですもん多羅尾伴内自体を、私世代ですら。
明智小五郎や金田一耕助は知ってますけど、多羅尾伴内って、私よりさらにご年配な方々の記憶にしか残ってないムービースターだと思うんです。
78年に本書を原作として小林旭主演で映画が二本撮られてるらしいんですが、興行的に失敗して、以降は一切音沙汰なしですしね。
旧シリーズにしたって映像作品として高い評価をうけ、後世にまで語り継がれてるというわけでもないみたいですし。
思い入れもなければ、知るべき動機も見いだせない状況で読んだところで目につくのはちぐはぐさ、荒唐無稽さだけ。
さすがにね、新聞記事をネタ元に正義を執行するため、わざわざ警察の捜査にでしゃばってくる私設探偵の話とか、許容の範囲を超えてるって話で。
今となってはもはや変人の部類ですよ、多羅尾伴内。
小池ファン、石ノ森ファンの双方から首を傾げられられそうな一作。
連載当時は映画の熱を引きずってそこそこの人気を博したのかもしれませんが、令和の時代にあっては過去の遺物と言っても大きく差し支えないのでは、と思える作品でしたね。
21世紀の狐
1977年初出 双葉社全3巻

殺し屋を殺す殺し屋、として闇社会に暗躍する元特別警護警察官を描いたクライムアクション。
うーん、殺し屋殺しなあ・・。
なんか舌噛みそうというか、一周回って結局は同じ場所に立ってるというか。
別に殺し屋のみ、と特定せず「悪辣な犯罪者どもを非合法に始末する闇のハンター」みたいな感じでいいと思うんですよね。
殺し屋ハンターとか言い出すから急に現実味が失せてしまうんであって。
主人公が自分のことを「狐」と名乗り、いつも狐面で現れるのにも関わらず、絶対顔隠しておいたほうがいい場面で必ずお面を外して素顔をさらす変なナルシスト?ぶりもちょっと気になった。
法の外側で生きてるのに、あちこちで素顔さらしまくってどうする、って話で。
これは楽しめないかもなあ、と思ってたら、中盤で突然「狐」が見ず知らずの女と籍を入れ「お前をもう一人の狐にする」とか言い出し、殺し屋の特訓を始める展開に急旋回し脱力。
実に小池一夫らしいと思いつつも、あまりなワイルドピッチに、ああテコ入れなんだろうな、とぼんやり考えたり。
そこからは夫婦殺し屋殺し(ああ言いにくい)のハンター道中膝栗毛ってな按配ですよ。
もちろん二人の間には激しい愛の炎がじゃんじゃか燃え盛ってるわけで。
予兆もきっかけも何もなかったけど、いつの間にそんな関係になったの?と疑問を挟む余地なんざなし。
ああ、これは絶対に女が死ぬな、と思って読み進めたんだけど、予想どうりだったかどうかはご想像におまかせするとして。
で、最終話ですよ。
主人公、狐は過去の怨恨を晴らすべく、謎の殺し屋集団に挑むため単独で渡米を決意するんですね。
おーい、I・餓男 アイウエオボーイ(1973~)やないかーい。
初期設定の冴えなさを挽回しようとがんばったが、状況考えずにいつもの手癖で物語をコントロールしたせいでかえってジリ貧に、といったところでしょうか。
どうでもいいけど田上憲治の作画が、昔の池上遼一にそっくりなのもアイウエオボーイの近似種化を加速してますね。
よほどの小池ファン向き、ですかね。
ケイの凄春
1978年初出 双葉社全14巻
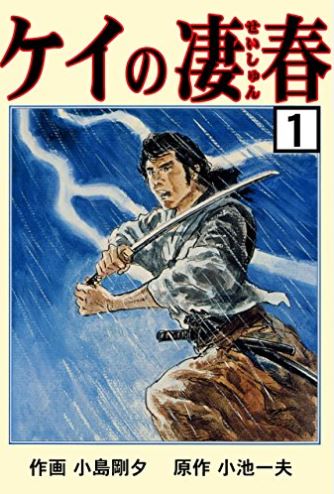
武家社会の体面やしきたりをなげうって、苦界に落ちた愛する女性の行方を捜し、食うや食わずの旅を続ける1人の元武士の姿を描いた時代劇。
あらためて書くまでもなくテーマは純愛です。
基本的に私は恋愛ものとか苦手な方で、ジャンルを問わず年々読まなくなる傾向にあるんですけど、それでもこの作品には舌を巻きましたね。
命がけなんです。
死と隣合わせに生をつなぎながら、1人の女性の面影をただ追い続ける。
うわついた感情なんて欠片もなし。
後ろ指を差され、さげすまれながらも、あらゆる苦難を乗り越えて一縷の望みにかけるその姿は、本気で人を愛するというのはどういうことなのか、饒舌に私達に語りかけます。
というかもう、読んでて泣きます。
あんたどこまでストイックでバカなんだ、と滂沱の涙。
ここまで辛酸を舐めさせておいて、二人が出会えない、なんてことになったら小池一夫殺してやる!とまで、読んでて感情移入してしまった私なんですが、そこはさすがに劇画の大家、きちんとクライマックスは用意周到にセッティング。
ものすごい画が待ち受けてる、とだけ言っておきたい、と思います。
さらにこの作品が凄かったのは、その後の顛末まできちんと描かれていること。
恋は熱病、なんてつっこみをいれる余地すらなし。
武家社会から脱落した人間が、その後、どう生きていくかまでをきちんと物語にしているんですね。
己を偽らず、人を欺かず、真摯に生きていくとはどういうことなのか、時代は違えどこれはもはや指南書の域。
子連れ狼を筆頭とする一連の作品とは真逆にある「生をつらぬく」こと、それを切々と語りかける大作。
文句なしの名作でしょう。
弐十手物語
1978年初出 小学館全110巻
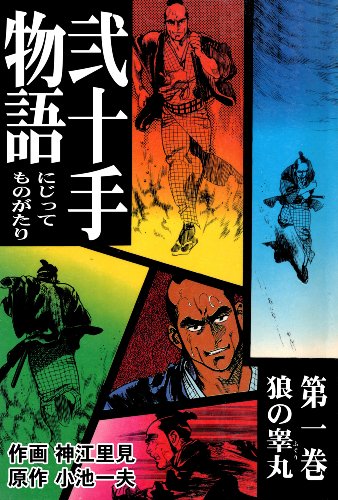
言わずとしれた小池時代劇の最長連載作、週刊ポスト誌上にて25年もの長きにわたって描かれた作品。
しかしまあよくぞ110巻も続いたことよなあ、と思います。
ぶっちゃけ110巻続くだけのことはある内容か?と問われれば微妙なラインだったりもしますしね。
20巻ぐらいまでは問答無用の大傑作だったと思うんですよ。
正しいことは正しいと、信念を曲げずに発していく主人公の同心、鶴次郎の命がけの捕物帖は、人情ものな側面も併せ持って心揺さぶられずにはいられない感動回の連続だった、と言っていいと思いますし。
身分制度と恥の文化が幅を利かせる封建社会下にあって、自分を貫くことの難しさは痛いほど伝わってきたし、まともなことがまともに通用せぬ理不尽さに憤る主人公のやるかたなさは強い共感を我々にもたらした。
意固地なバカのくせに、優しすぎるんだよ鶴次郎・・・と何度目頭を拭ったことか。
あ、なんかちょっと面倒なことになってきた、と私が思ったのは、小池劇画必殺のパターン「惚れた男に身を挺して女たちがバッタバッタと死んでいく」をこの作品でも作者がやらかしたこと。
一人や二人ならまだいいですよ。
もう両手で数えなきゃなんないくらい女が死んでいくんですよ。
まあ、それこそが死神鶴次郎の異名そのものを体現してたりはするんですけど、それにしたって殺しすぎ。
挙げ句には登場してくる女性キャラが片っ端から鶴次郎に惚れちゃうものだから、主人公、貧乏同心のくせに一夫多妻制をこの時代にやらかす羽目に。
その間にも次々と女は鶴次郎の代わりに凶刃を受けて死んでいく。
で、複数の妻もようやく減ったかと思うと、また新たな女性キャラが鶴次郎に惚れて第7婦人だか第8婦人だかに収まる始末。
それでいて大勢の妻たちはお互いに嫉妬することが全くない、って、もうカルト教団状態じゃねえかよ!と思うわけです。
鶴次郎がおかしな具合に神格化しちゃってるんですよね。
正直、20巻~40巻ぐらいまではマンネリ化しつつあった、といっていいでしょう。
ただ、そこでなげやりにならない、しぼまないのが小池一夫のしぶとさでして。
死にゆく女達のお涙頂戴路線はそのままに、鶴次郎自身を時代の不合理と戦わせるために奉行所を飛び越えて、寺社奉行や老中、目付と正面から激突させるんですな。
鶴次郎の人権主義と正義感、心優しさはこの時代、どこまで通用するのか?を直接権力の中枢にぶつけてみて量る、という作劇。
もう、命がいくつあったって足りやしない。
最終的には徳川吉宗と接見を許され、語らい合う場面にまで至る始末。
ありえねえ、と思うんです。
でも、ありえなさがゆえに人の性善性を信じたくなってくるドラマとスリルがあったことは確か。
なんだこの漫画、鶴次郎に革命を起こさせようとしてるのか?薩長同盟が存在しない無血開城なもうひとつの世界を描こうとしてるのか?!とあたしゃ正直焦りましたね。
手札の切り方も全く惜しみなし、で。
公儀御庭番は味方になるわ、吉原は手中に治めるわ、黒鍬者に風魔に柳生と、登場しないのはお毒見役安倍頼母ぐらいのもの。
もはや哲学の領域か、と私は途中で思ったりもした。
鶴次郎がよく口にする「人は生かされている」というセリフを時代劇というフィルターを通して具象化しようとしてる節さえあるな、と。
結局の所、一介の同心である鶴次郎が巨大な勢力のバックアップを得て、それをどう行使するか、深堀りしなかった時点でテーマは完遂されなかったんですけどね。
そして90巻ぐらいからは再びマンネリというか、ワンパターンな路線に。
大奥に阿芙蓉が蔓延する話を2回描いたり、前話での設定を忘れて、いつのまにか鶴次郎が普通の同心に戻ってたり、死んだ鶴次郎の妻の数が合わなかったり。
ああ、もう息切れしちゃってるな、と。
全部描きつくしちゃったんだろうな、と。
小池一夫が超人を主人公に据えず、普通の男の真正直な生き様を剣技に頼らず描こうとしたことが長期連載に至ったことは理解できたんですが、話を膨らませ過ぎた割にはどこにも着地しなかった印象ですね。
ちなみに110巻の最後には<第一部完>と記されてます。
110巻描いて第一部って・・・。
カムイ伝も裸足で逃げ出す悠長さだ。
いや、勤勉なのか?
どちらにせよ、もう満腹。
多分、魔物語愛しのベティ(1980~)と近いことがやりたかったんだろうと思うんですけど、時代劇の制約を鶴次郎自身が突き破れなかった時点でこの物語はもう永遠に終わらないんだろう、と思います。
序盤が素晴らしい出来だっただけに、終わり時を見極めてほしかった、というのが正直な感想。
*画像をクリックすると電子書籍の販売ページへと飛びます。0円で読めるものも多数あります。

