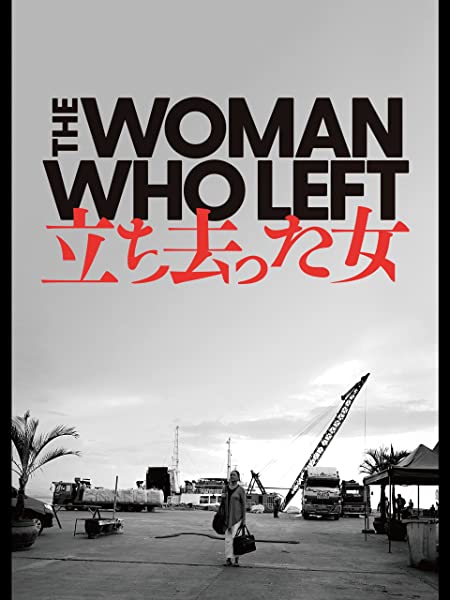イギリス/ギリシャ 1967
監督、脚本 マイケル・カコヤニス

わずかな数の島民がほそぼそと暮らすギリシャの小島に、小型核兵器を積んだ軍用機が墜落したことによって巻き起こるドタバタを描いたブラックコメディ。
背景にあるのは言うまでもなく、世界大戦後に険しさを増していった米ソ冷戦による軍備拡大。
それを強烈な皮肉と笑いで包んだのが本作と言えるでしょうね。
ま、こんなプロットを普通に料理した日にゃあ、とんでもなくシリアスで悲痛な内容にしかならないと思うんですが、そこは巨匠カコヤニス、クソ真面目にやってどうする?!とばかり序盤から悪ふざけ全開です。
実は軍用機、墜落するにはしたんですが、核兵器そのものは墜落前に島へ投棄されたんで爆発はしてないんですね。
そこに命からがら脱出したパイロット二人がパン一で上陸してくる。
島民に軍用機が墜落したと知られてはならないからパイロットスーツを着れないわけです。
以降、この二人、映画が終わるまでずっとパン一。
なんとか母国の司令部に連絡を取りたいたいのだけど、パン一だから人前に出れないし、当然電話代も持ち合わせてない。
延々、人気のない島の山間部を、ああでもない、こうでもない、とうろうろするばかり。
もうね、この二人だけで映画一本撮れてしまうんじゃないか?ってぐらいバカバカしくて爆笑です。
絵ヅラがね、ずるい。
登場するたびに笑いが漏れてしまう。
そうこうしているうちに軍本部が極秘の捜索部隊を島に派遣。
そこからの展開は怒涛です。
詳しくは書きませんが、中途半端に捜索部隊であることを隠して行動したものだから、外に漏れる情報が捻じ曲がってしまい、いつしか寂れた小島は世界中から人が押し寄せてくるリゾート地に。
核兵器の捜索どころじゃない終盤の乱痴気騒ぎは、まさにドタバタの真骨頂とも言える「狂騒の極み」を演出します。
まあ、とにかくうまいですよね。
誤解が誤解を生む筋立ても見事ですし、村人、捜索部隊、パン一の二人、キーマンとなるヤギ飼いの夫婦、主要登場人物四者の関係性にも巧妙な計算が見て取れる。
構成も無駄なく完璧、随所でギャグを挟むことも忘れない、それでいて暗示めいた描写も含んでたりもするんだから、どこまで手練なんだよ、って話で。
で、特筆すべきはやはり衝撃的なエンディングでしょうね。
ここでようやく我々は、不可解なタイトルの意味を思い知らされます。
薄ら寒い、とはまさにこのこと。
一挙急転した物語の色調の変化に激しく動揺させられながらも、すべてはこのエンディングのための壮大な前フリだったか!と私は震え上がりましたね。
無知で蒙昧であることを呪い、無責任で無関心であることをも蔑むかのように見える物語の帰着点は、単に反核映画の枠組みに収まりきらぬ雄弁さを隠し持ってる、と言えるんじゃないでしょうか。
文句なし、傑作だと思います。
笑わせて笑わせて、最後の最後で冷水をぶっかける、これぞブラックコメディと言える一作。
必見でしょう。