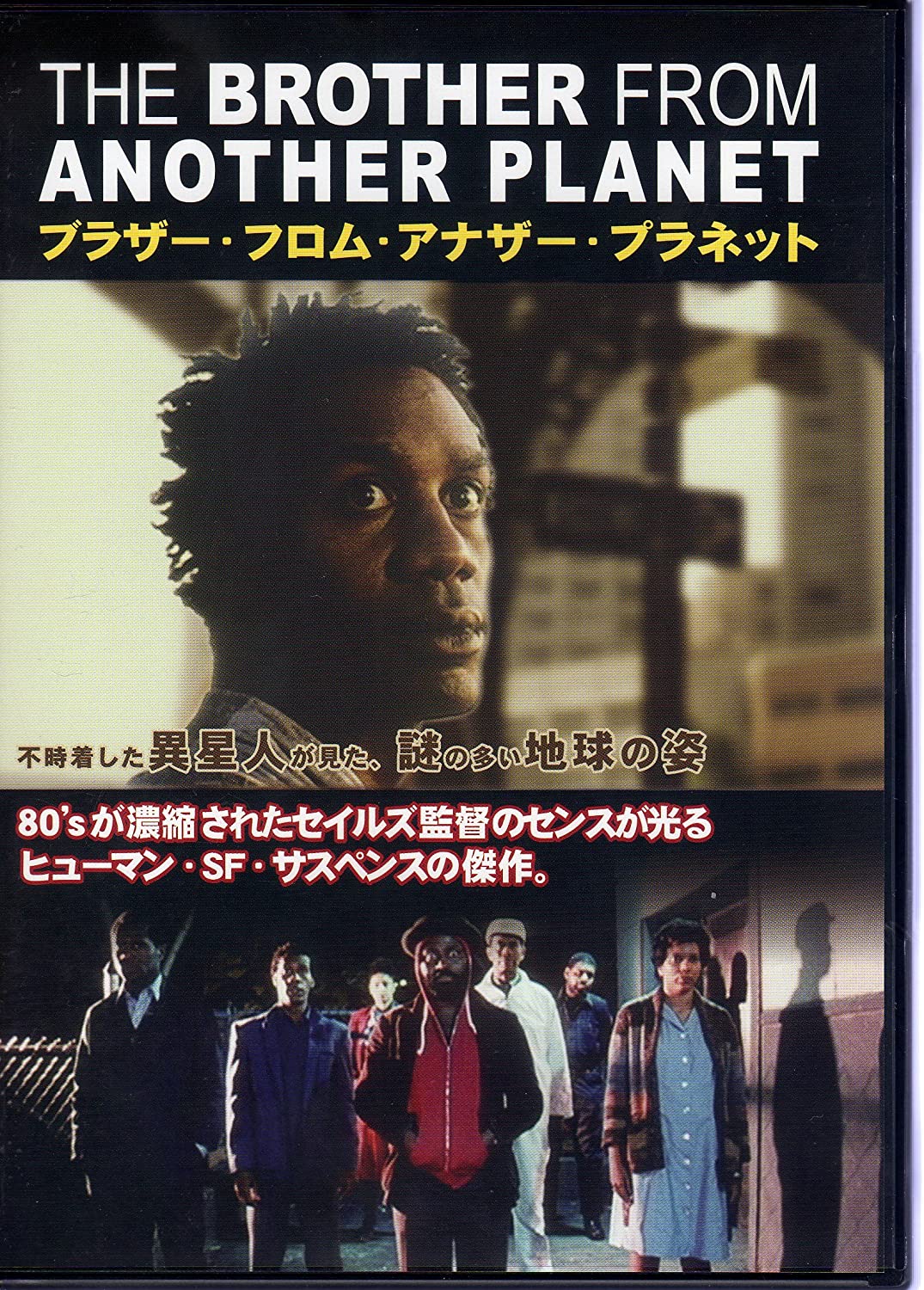アメリカ 2016
監督、脚本 マイク・ミルズ

思春期を迎える息子をどう教育すればいいのか悩んだシングル・マザーであるオカンが、自宅に下宿する写真家のお姉さんと、幼馴染みの女子高生に「息子の助けになってやって」と、母親の役割を分担、共有しようとするお話。
いやいや普通に考えて必要とされてるのは男親の代役であって、間違っても年上のお姉さんと同級生じゃないだろう、と即座につっこめてしまうあたりに観客の興味をくすぐる奇妙さがあるわけですが、その奇妙さが最終的に「ならではの結末」を導き出したか、というと別にそういうわけでもない、というのがこの作品の難かしさでしょうね。
少年、年上のお姉さんと同級生に翻弄されて、これまで以上にわけのわからない状態に陥ります。
なんせお姉さんはフェミニスト気味な写真家で、同級生は自分自身が迷走気味。
どう考えても上手くいくはずがない。
オカンは「まだ15歳なのよ、あなたの教えることは早すぎるわ」などと、あれこれくちばしを挟むんですが、そもそもそういう人物を選んだのはあんただろうが、って話で。
結局のところ、主眼が置かれているのは、オカンの「変さ」であり「わけのわからなさ」なんですね。
こういう風変わりな母親も居るんだよ、ですべてが完結しちゃってる。
そこからどこへも行かない。
なんだか私小説的で回顧録みたいだなあ、と思って調べてみたら、この作品、監督が自分の母親を題材とした半自叙伝的な内容だとか。
なるほど納得。
そりゃ、どこへも着地しないはずだわ、と。
で、これが面白いのか?ってことなんですが、個性的な人物たちが織りなす80年代の在りし日の風景は、少年の目線を通してみずみずしく描かれていた、と思うんですが、だからどうした、と言ってしまえばそれまでな気もしなくはない。
出色だったのは変な母親を演じたアネット・ベニングの演技で、この人はなんという表情をするんだろうと感嘆したんですが、それだけ、と言ってしまえばそれだけだったり。
なんとも評価しにくい作品、というのが本音ですね。
退屈することはなかったんですが、まーしかし、色んな家庭があるもんだなあ、で私の場合終わってしまった。
会話劇における台詞回しのセンスの良さや、ノスタルジーを喚起する細かい演出は評価したい、と思うんですが、どこかウェス・アンダーソン監督作品にも似てクセがあるようにも感じました。
はまる人は猛烈にはまるかもしれませんね。
私は幾分ぴんときてなかったりもしますが。