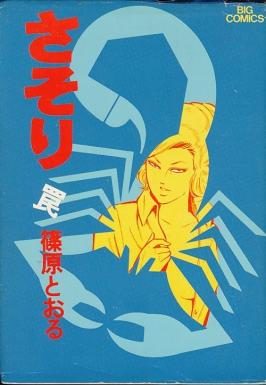イギリス 1975
監督 スタンリー・キューブリック
原作 ウィリアム・メイクピース・サッカレー
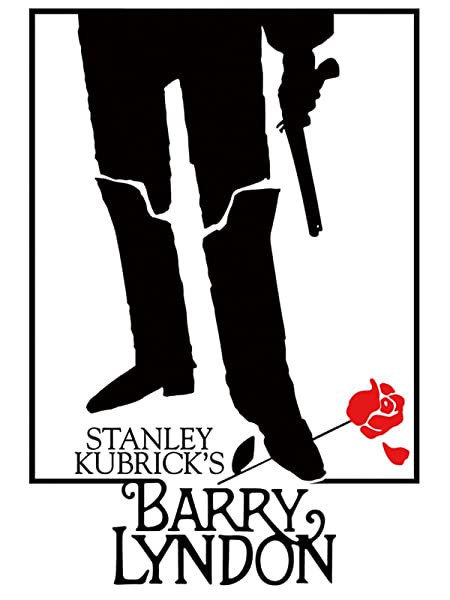
18世紀のヨーロッパを舞台に、アイルランド出身の農家の小倅が世渡りのうまさと人柄を武器とし、貴族さながらに成り上がっていく様を描いた伝記的作品。
すでに語りつくされていますが、徹底してこだわりぬいた当時の風俗や衣装の再現は監督ならではだと思いますし、 自然光やろうそくの火を光源として撮影された映像も誰もが認める絵画的レベルにある、といって間違いないでしょう。
そこはもう、品格、という言葉すら思い浮かんでくるほど。
うまくいきそうでなかなかうまくいかない押し引きのあるシナリオ展開も、3時間という長丁場を飽きさせないだけの起伏に富んだものだった、といえると思います。
ちゃんと要所要所に見せ場を用意してるのがまた心憎い。
やっぱり日本人としちゃあ18世紀の戦火にさらされたヨーロッパって、あんまりなじみのないものだと思うんですよ。
でもそこを監督は、門外漢が見てもきちんと伝わるものがあるように工夫してるんですね。
ダブルスパイを演じる羽目になるシュバリエとの面会のシーンや、終盤、病床のわが子に嘘八百の武勇伝を聴かせるシーンなど、歴史的背景がわからなくても充分心揺さぶられるものがある。
この手の文芸作品っぽい映画でこういうことが出来てしまうのって、名匠キューブリックだからこそだと私は思います。
ただですね、なんら批判する材料は見当たらないと確信する私が唯一ひっかかったのは、ナレーション主導でストーリーが進んでいくこと。
長大なヴォリュームを誇る物語ですんである程度の解説は不可欠だったんだろうと理解はできますが、ナレーションが先の展開を説明する不粋なマネをしばしばやらかしてて、それが興ざめを招く、ってのは幾分あった。
そこはもう少し観客を突き放しても良かったんじゃないか、と。
時代もあったのかもしれませんが、監督なら必要最小限の解説であとは映像で語る、ってできたと思うんですよ。
なんせ2001年宇宙の旅であれだけのことをやらかした人ですし。
いまひとつこの作品が映画好きの口の端にのぼらぬのはそういうところも影響してるのかなあ、と感じたりはしました。
あとはオチですかね。
今みるとああこのパターンね、と鼻で軽くあしらってしまう人も中には居るかもしれません。
でもそれは模倣する奴が多すぎたせいであって、この作品のせいじゃないわけで。
敷居が高そうに思われがちな一作だとは思うんですが、そこは食わず嫌いをやめてですね、かまえずに見てほしい、と思いますね。
それに答えられるだけの魅力、懐の広さは充分にある。
なぜ主人公バリーは、義理の息子との決闘のシーンであのような決断を下したのか、考えてみるのも一興かと思います。
単に伝記をなぞっただけの映画じゃない、ときっと気づいてもらえるはず。
私はこれもまたキューブリックの秀作、と思いますね。