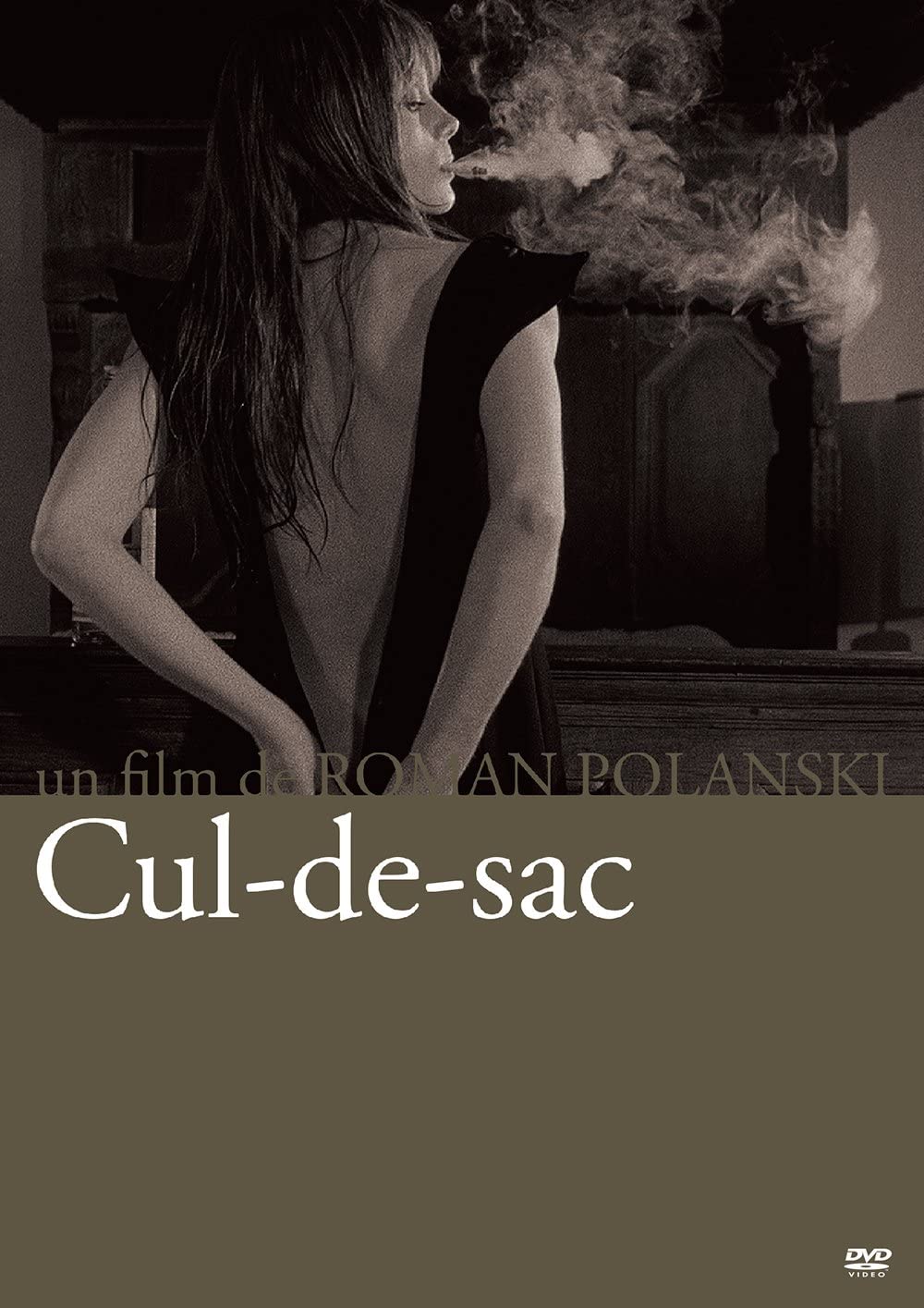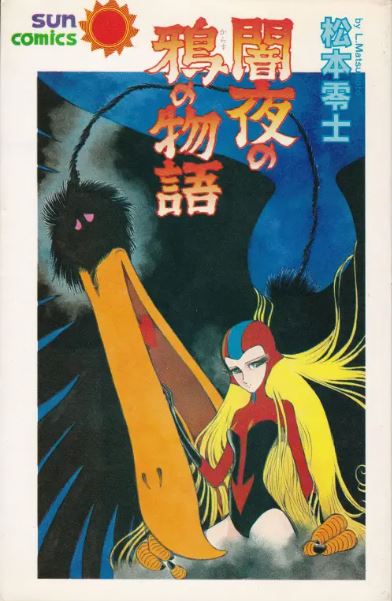イギリス 1966
監督、脚本 ロマン・ポランスキー
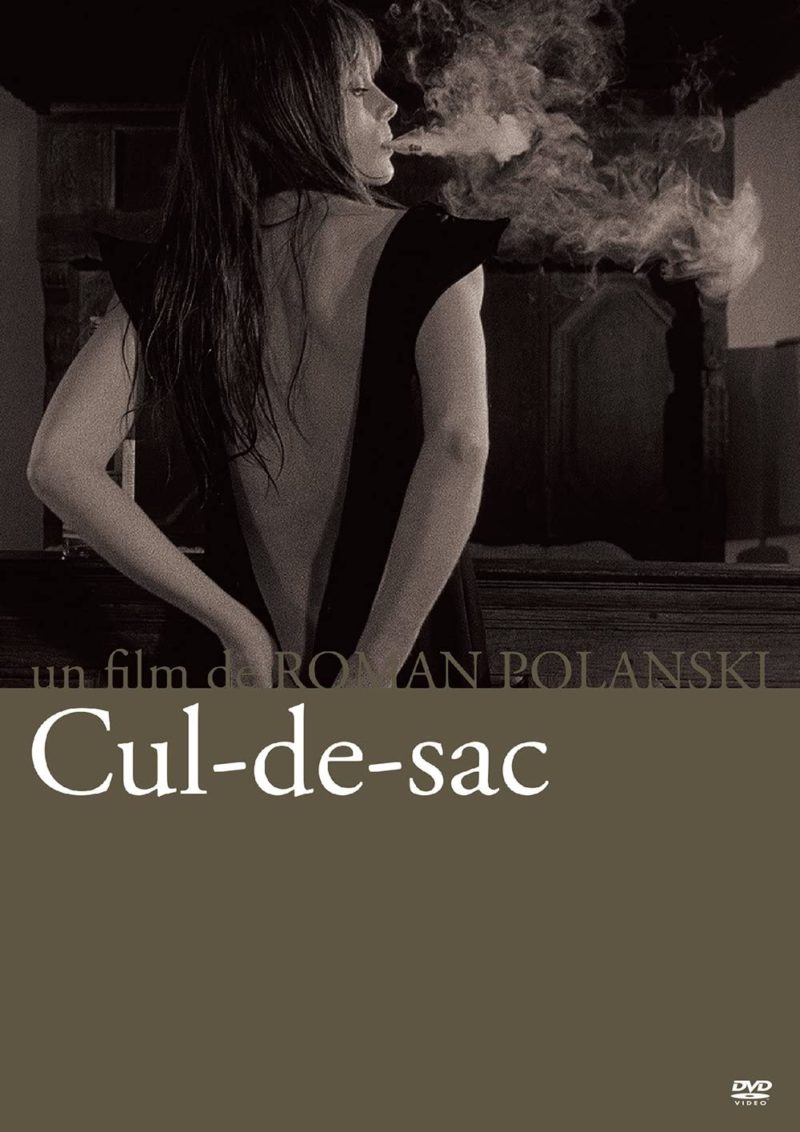
コメディといわれればコメディかも、と思えなくもないんですが、登場人物のどこか屈折した描写はなにか含むものがありそうで、うかつに笑えない、というのはありますね。
金持ちの芸術家気取りが、若い妻を連れて孤島で楽園を実現しようとしたところに、意外な闖入者が現れて、はからずも理想の暮らしが崩壊していく様を描いた作品なんですが、あ、うまいな、と私が思ったのは、闖入者が一番まともそうに見えるよう撮られていること。
いや、闖入者、ろくでもないやつなのは確かなんです。
拳銃を振り回して力づくでいう事を聞かせようとするような輩ですし。
でもその振る舞いに姑息な計略やつまらない嘘がなくて、欲求に正直に、何事もシンプルかつストレートなんですね。
荒くれ者だがどこか愛すべきわかりやすさがある、というか。
社会的には成功者といっていい夫婦と闇社会に生きる闖入者の対比、これがステロタイプながらある種の問いかけを観客にせまっているように私には感じられました。
象徴的なのはエンディング。
きっと闖入者はそこまでやるつもりはなかったはずなんです。
だが孤島の館の主は、はずみで一線を越えてしまう。
この救いのないラストシーンの意味するものはなにか。
解釈は様々かと思いますが、私はなんとなく「虚構の楽園」と言う単語が脳裏をよぎったりしましたね。
来客にあわてて即席の芝居をうつシーンも見どころのひとつ。
島の館を取り巻く美しい風景とコメディ調ながらアイロニカルなシナリオが印象的な秀作だと思います。