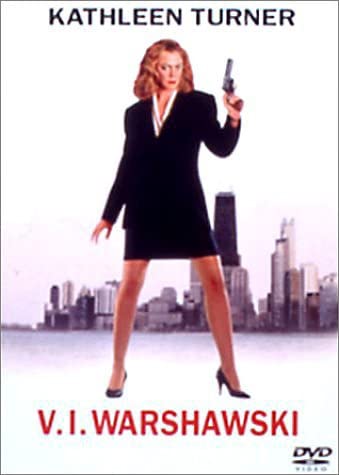アメリカ 2017
監督、原案 ジェームズ・マンゴールド

さて実は私、X-MENシリーズにほとんど関心を持ってない、という人でして。
一応、最初期の1作か2作は見た記憶があって、そのおかげでウルヴァリンというキャラは知ってるんですけど、X-MEN全体の物語の流れはさっぱりわかっておりません。
なんか悪い奴らが居て、そいつらにミュータント軍団が立ち向かうんでしょ、程度の認識。
なんでそんなに突き放した感じなのか、というと、いわゆるミュータントという存在自体に入れ込めないから、に他ならなりません。
私の感覚じゃ、目から光線が出たり、嵐を巻き起こしたりする特殊能力をもつ亜人類達が主人公、というプロットそのものがね、いったい何十年前のネタなんだ、って感じで。
まあ早い話が超能力者でエスパーなわけです。
70年代、大流行しましたよね。
日本でも超能力者を題材とした作品はアニメを筆頭に立ち腐れるほど量産された。
色んなアイディアを盛り込んで独自に進化を遂げたその手のジャンルは、AKIRAをトドメとして90年代に終焉を迎えた、というのが私の認識。
もちろん嚆矢となったのはコミックの世界じゃX-MENなんでしょうけど、それをなぜ今更実写でやらねばならんのか、と言った点が当時私はひっかかったんですよね。
有り体に言うなら、悪い意味でマンガっぽい。
マンガが駄目だと言ってるわけじゃないんです。
マンガみたいな世界観を実写映画にそのまま持ち込んでどうする、と言いたいわけです。
正直、1作目を見た時、笑わせたいのか、と呆れたこと数度。
なので本作を視聴するにあたって、ウルヴァリンに対する思い入れだとか、好感度なんかはほぼゼロ。
なんせ以前偶然見たスピンオフ、ウルヴァリン・SAMURAIがあのザマでしたしね。
期待しろ、という方が難しい。
ところがだ。
そんな私の斜に構えた態度は見始めて数十分で大きく覆されることになる。
えっ、ウルヴァリン、なんかヨレヨレやん。
リーダーだったじいさん、ボケてしもとるがな。
特に私が興味をそそられたのは、人あらざる能力をもち、人を越えかねない存在だったはずの二人が「老い」に直面して自らの能力が逆に足枷となっている設定。
超能力を思う存分発揮して大活躍、って作品は大量にあると思うんですよ。
でも、当事者の晩年に焦点を当てて、能力をコントロールできない苦悩を描いた作品、ってなかったんじゃないか、と。
そこから浮き彫りになってくるのは、かつてはヒーロー視されたはずの超人性をいびつに変質させた「異形」であるがゆえの悲哀。
なんだこれ、私が滅茶苦茶弱いパターンの物語図式じゃねえかと。
なんかもう、ミュータントとかそういう突飛な原案をすっとばして「ドラマ」なんですよね。
さらに私が驚かされたのは、そこに小さな救いとして、同類の少女を放り込んだこと。
序盤以降の展開、みなさんおっしゃってますが、ほとんどロードムービーです。
世間の理解の外側にある3人が、身を寄せ合うように、あるかどうかもわからない希望の地に向かうシナリオ進行に、惹きつけられないはずもなく。
また、容赦なく残酷に、血飛沫散らして死線をかいくぐるアクションシーンが随所に挿入されてるのにも舌を巻きました。
逃げてばかりじゃダレるからフックとして、って感じじゃないんです。
本気で異能の戦いぶりを演出しようとしてるこだわりがあるんです。
私なんざ、これ、アクション監督が別に居たのか?と思ったほど。
そして何よりも素晴らしかったのがエンディング。
最後の最後まで引いて引いて引きまくって、ようやく少女とウルヴァリンの間に通う感情を表出させたクライマックスシーンに涙腺は怒涛の決壊。
大人げないオッサンだなあ、そりゃ色々つらいこともあったんだろうけど、なにも外の世界のことを知らない少女に対して冷酷すぎやしないかウルヴァリン、と私はちょっと思ってたりもしたんですが、それも全てはこのエンディングのためだったか、と思うと監督の手際の鮮やかさにほとほと感服しました。
手っ取り早い感動を小出しに安売りしようとしてないんですよね。
ケレン味たっぷりなオールドスクールのSFを、滅びゆくものの哀切を描いた物語として転換、昇華させた傑作でしょうね。
もうほとんどこれ、あの頃のアメリカン・ニューシネマじゃないか、と思ったりもした。
ヒュー・ジャックマンの熱演も必見。
X-MENに興味のないあなたが見ても全然大丈夫、と私、太鼓判を押させていただきます。