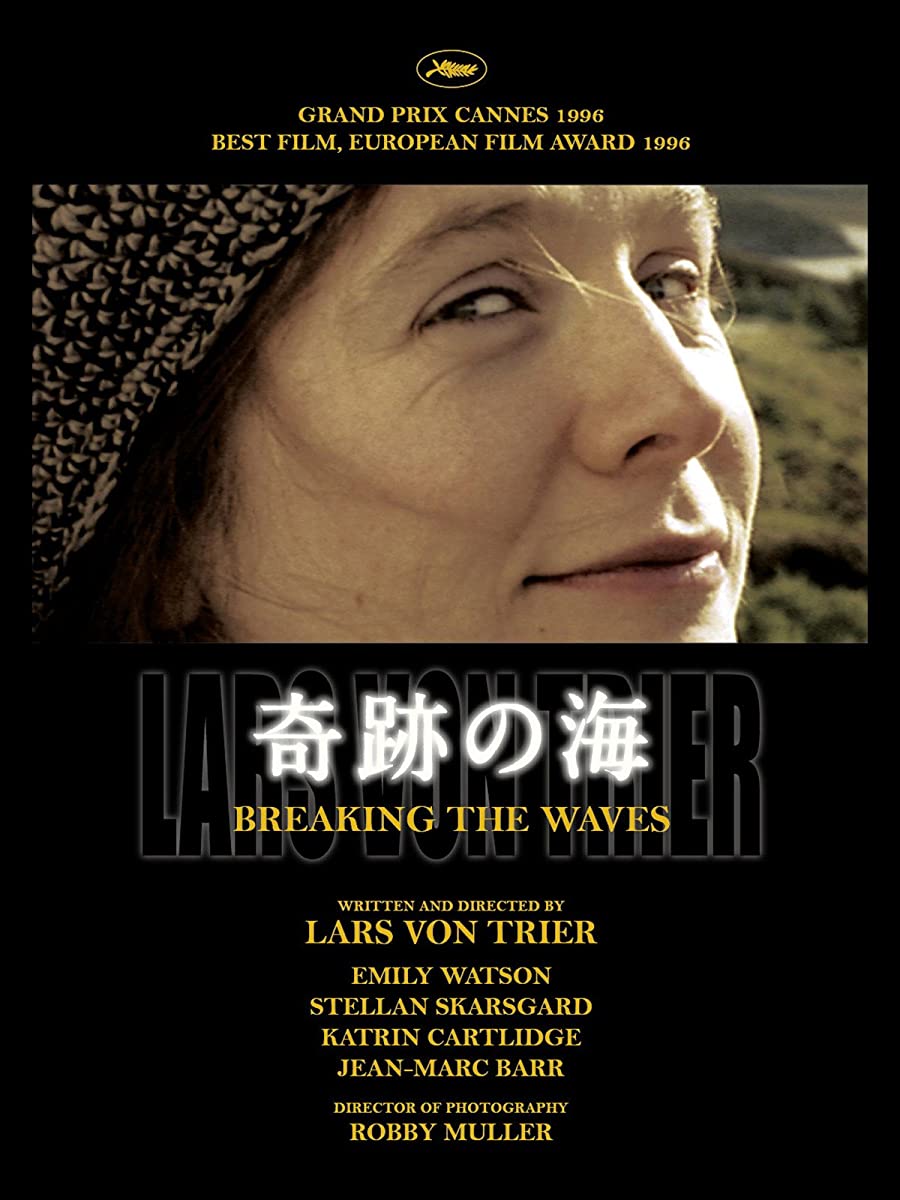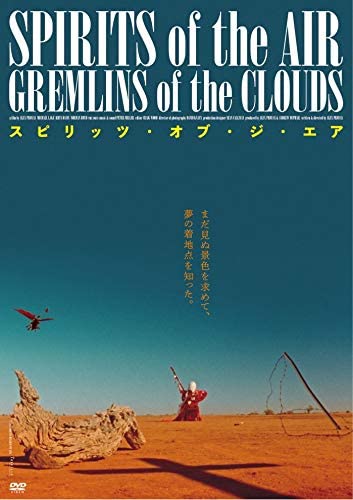スウェーデン 2015
監督 ハンネス・ホルム
原作 フレドリック・バックマン

妻に先立たれ、職場からも解雇、生きる希望を失った孤独なじいさんと隣人たちの交流を描いた人間ドラマ。
どちらかといえばありがちな題材でプロットです。
人の言うことに耳を貸さず、口を開けば嫌味ばかり、地域のルールを守らないやつは許しておけない頑固じじいが、偶然隣に越してきてきたペルシャ人一家のおせっかいのおかげで少しづつ協調性が芽生えてくる、と言うストーリーは、あれ?似たような映画なかったっけ?とばかりに既視感たっぷり。
じいさん、先立った自分の妻にしか心を許してないんで、退職を機に妻の元へと行こうと自殺を企てるんですが、それを尽く騒がしい隣人に邪魔される展開もどこかハリウッドコメディ調で、なんか見たことあるような・・って感じでしたし。
良くも悪くも北欧映画っぽい質感はあまりない。
ただ、それがとっつきやすさにつながってるのは確か。
そのまま表層的にありもしない希望をちらつかせて、人は1人じゃ生きていけないんだよ、和を持って尊しだよ、みたいな場所に物語を落とし込んでいたなら確実に3日で忘れるパターンだったと思うんですが、監督が上手だったのはそんな先の展開が予想できる筋立てに、なぜじいさんはそういう人間になってしまったのか、1人の男の人生を子供時代から振り返る形でじっくり描いていったことにあるといっていいでしょう。
適当な不幸を過去に散らつかせて、でもそれに負けてちゃダメ、みたいな説教口調でじいさん改心、じゃないんですよ。
安いカタルシスでお茶を濁してない。
じいさんがそうなったのは、そうなるだけの理由があって、それを踏まえた上での晩年を彼はどう生きるべきなのか、という問いかけが作品にはあるんです。
見たまんまの扱いづらい頑固じじいが主人公の実像ではない、としたところにこの作品の奥深さがある。
だから、多分こうなるんだろうな、という方向に物語が進んでも、背景に用意されたものが膨大だから説得力が違う。
そこは掘り下げ方の丁寧さ、ドラマ作りの緻密さの勝利でしょうね。
めでたし、めでたし、で締めくくらないエンディングもいい。
このエンディングのおかげで、市井に生き、愚直に43年を鉄道局職員として勤め上げた男の「あがき続けた人生」を描くことが本当の主題だったのだ、と我々は思い知らされます。
ラストシーン、泣かされます。
いきなりこんなの持ってくるなんて卑怯!と、私は年甲斐もなく嗚咽を漏らした。
頑固じじいの老後をハートウォーミングにつづるように見せかけておいて、実はそうじゃない、というのがこの作品の独創性でしょうね。
ちょっと大げさかもしれませんが「生きること」と真摯に向き合った作品だと思います。
主演のロルフ・ラッスゴートの細やかな演技も見事。
北欧映画の枠組みから飛び出した秀作でしょう。
こういう映画こそを三大映画祭は評価すべき、と私は思いますね。