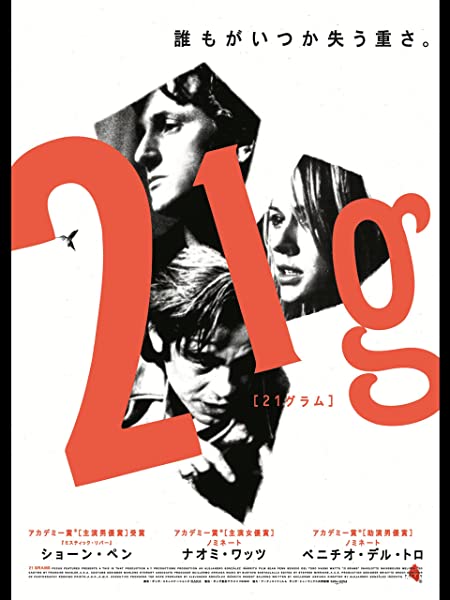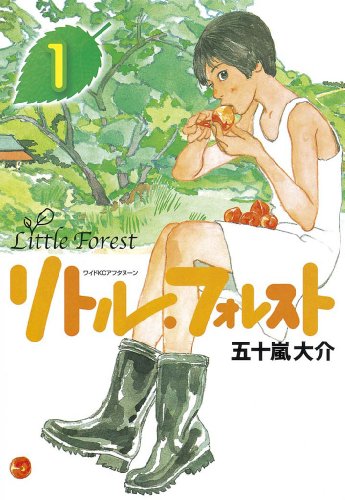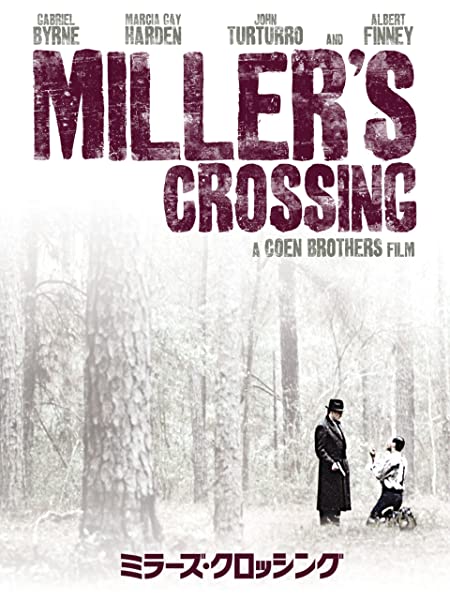アメリカ 2006
監督 アレハンドロ・G・イニャリトゥ
脚本 ギジェルモ・アリアガ
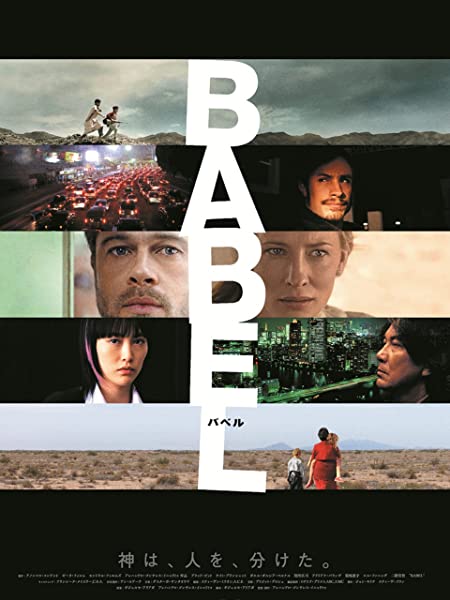
しかしまあ、この監督はつくづく群像劇が好きな人だなあ、と。
今作もデビュー以来おなじみの調子で三つのドラマが同時進行。
日本、モロッコ、アメリカと舞台を別にして、時間軸は過去と現在を行き来する。
それぞれの物語をか細い糸で結びつけるのは一挺のライフル。
いうなれば、最初の持ち主の手を離れたライフルが、その後、どのように数奇な物語を紡いでいったかを連綿と綴った、と言っていいのではないでしょうか。
短絡的な見方をするなら、アメリカという歯止めの見当たらない銃社会に対するアンチテーゼ、と受けとめることも可能か、と思うんですが、 それにしちゃあストーリーに色々雑味がありすぎる。
そこまで一本調子にわかりやすい内容でもない。
なによりもひっかかるのはタイトル。
なぜこれがバベルなのか、という点が、バベルの塔の逸話を鑑みてみても内容とリンクしないんですね。
言語による断絶をテーマとすることがバベルの意味するところだ、と言いたいのかもしれませんが、それならば断絶を経て、神々を怒らせた人々はなにを贖罪としたのか、もしくは、神々そのものを唾棄してしまったのか、それとも忘れてしまったのか、その関係性の帰結を描く必要がある、と私は思うわけです。
このシナリオだと、人々は罪深い、以上、なんですね。
そこに断罪もなければ救いもない。
ただただ非遇な巡りあわせに翻弄された市井の人たちの痛ましいドラマをつらつらと並べただけ。
やっぱり私なんかは、だからどうしたんだ、だからどうだというんだ?と、どうしても思ってしまう。
3つのストーリーを別々に見るなら実に見ごたえがある事は確かなんです。
銃を手にしたモロッコの少年のほんのいたずら心が招く悪夢的現実も、メキシコ人の乳母の何気ない選択が驚きの展開をみせる荒地の逃避行も、聾唖の女子高生の苦悩を描いた日本のさもしい現実もすべて心に響くものがあった。
要はなぜこれを全部一緒にやろうとするのか、という話で。
辛辣に言ってしまうなら、やはりすべてを統括できてない。
なんかもう、色々もったいない、の一言ですね。
甚大な労力を費やして、丁寧に作ってるのがわかるだけに。
21gで、次の領域にひとつ駒を進めた、と私は感じたんですが、また逆行してしまった印象。
人並み以上にできるのに、それがなぜか形として結実しにくい監督、と感じるのは私だけでしょうか。