アメリカ 1990
監督 ジョエル・コーエン
脚本 コーエン兄弟
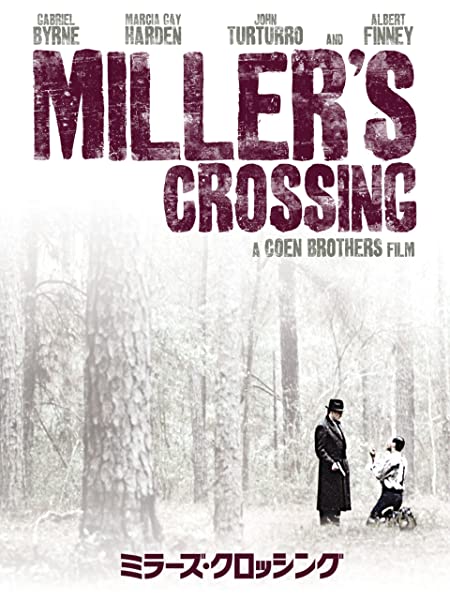
1929年のアメリカ東部の街を舞台に、マフィア同士の抗争の狭間でギリギリの駆け引きを演じる、若きギャングの奸計を描いた作品。
基本、私はマフィアものってあまり好まないんですが、この作品に限っては、自分でも意外に思えるほど熱中して見てしまいましたね。
あれ、なんだこれ、ちょっと違うぞ、って。
えてしてこの手の映画って「成り上がり」と「その後の破滅」を描くのが多いように思うんですが、同じ轍を踏むように見せかけて、コーエン兄弟は巧みに物語をセオリーとは別の方向に誘導していたように思います。
そこがまず、新鮮に感じられた、というか。
誤解を恐れずに言うなら、これ構造的には黒沢明の「用心棒」とどこか似てるんですね。
敵対するマフィアの間で策謀をめぐらせ、上手にボスを自分にとって有利な方向へといざなう展開とか。
もちろん、そこに正義の行使なんて存在するはずもなく、全ては自分の保身の為から、という点がまるで用心棒とは違うわけですが。
しかしながら、目的が保身という利己的な露骨さであったがゆえ、それがひりつくような切迫感と先の展開の読めない緊張感を産んでいたことは確か。
ろくな人間が出てこないんで、誰が途中で死んでも全然おかしくないんですよね。
それは危地における主人公も同様で。
計算高いようにみえて、どこかいきあたりばったりな感情先行型である、という人物像もスリルを倍化。
やっぱり登場人物たちを肉感的に描くのがやたらうまい、というのは感じましたね。
キャラクター作りが達者なのもさることながら、このキャラクターならこういう状況下においてどう動くか、という部分に無理がないし、それが結果、十重二重に錯綜するストーリーを、これはないわ、と興ざめさせないんですね。
実はこの物語、まずキャラありきでここまで複雑に立体化していったのではないか、と勘ぐったほど。
全体をコントロールする基礎体力が圧倒的に高い、と私は思った。
ただ、唯一、難点をあげるとすれば、やはりエンディングでしょうか。
主人公トムはなぜあんな選択をしたのか。
そこは観客の想像に任せる、でいいのかもしれませんが、個人的にはなにがしかの心情の吐露で最後は決めて欲しかったように思います。
一番肝心なところでボールをあさっての方向に投げてしまったように見えるんですね。
トムが最後に感じたことはなんだったのか。
それがわずかにでも伝わるアクションがあれば名画の領域に足を踏み入れていた、と思うのは私だけでしょうか。
まあ、そこを差し引いたとしても凡百を凌駕するおもしろさ、なのが凄いところではあるんですが。
さすがはコーエン兄弟、と唸らされる一品でしょう。

