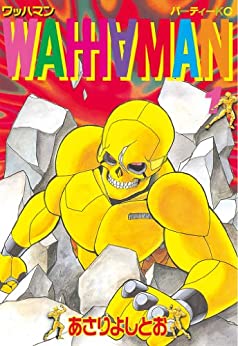韓国 1998
監督、脚本 キム・ギドク

この作品あたりから異才キム・ギドクの作風に徐々に彼らしい色がついてきたような気が私はしてます。
海辺の民宿で、泊り客の夜の相手をつとめる娼婦を描いた作品なんですが、これってもう完全に一昔前の日本の行楽地の裏側、そのままだよなあ、とまずは海外の作品とは思えぬ既視感。
描かれてるのは性も欲望も正も邪も、すべて渾然一体となった生々しい生活そのもの。
誰もが適度にくたびれてて、誰もが決してそれが真っ当な事だと思っていないのにも関わらず、そこから抜け出せずにいる。
そこに波紋を投げかけるのが民宿の娘なんですね。
彼女は両親がふしだらな娼婦を民宿の売りにしてることをひどく嫌い、ことごとく娼婦に辛くあたるんです。
その反面、もし娼婦が居なくなったら、自分も親も生活が立ち行かなくことが彼女はわかってる。
民宿の娘はどうやって現実と折り合いをつけるのかが見どころなわけですが、序盤の展開からこんな場所に物語を誘導するのかと、ひどく驚かされた部分はありましたね。
なぜ民宿の娘はストーリーが進むにつれてあのような形で変節したのか、その心模様を描写しきれてない、と感じた部分もあったんですが、それ以上に私は、きれいごとやわかりやすいモラリズムだけで生を重ねていくことはできないのだ、とした監督の達観した目線に感心させられた。
いわゆるフェミニストであるとか、男女共同参画とか、その手の思想に傾倒した人にとっては腹立たしい内容かもしれません。
でも私は、それが女性であるから、と言う理由を超えて監督が正面から見据えているのは、泥をすすりながらもひるまずその場で生き抜こうとする人本来の営為そのものであるように思えた。
そこに後ろ暗さはあっても、薄汚さはないんですね。
すぐ欲望に流されちゃうダメな登場人物たちに向けられる、奇妙な慈しみに満ちた視線にも心動かされるものがあった。
後年の作品ほど強烈な説得力があるわけではありませんが、どこか感じ入るものがあったのは確かです。
かつての良質な日本映画の佇まいがある、というと誤解を受けるでしょうか。