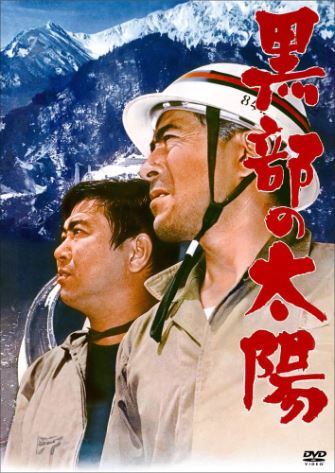日本 1962
監督 小林正樹
脚本 橋本忍
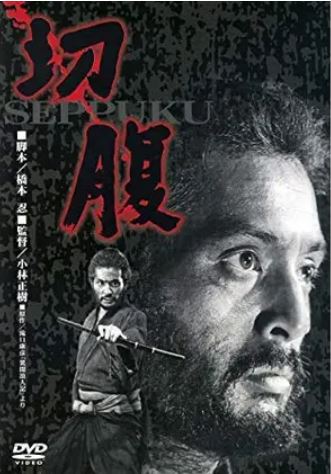
食い詰めた貧乏侍の死を巡って、主家家老の欺瞞を追求する一人の浪人の姿を描く時代劇。
なんといっても独特なのは物語のプロットでしょうね。
まず前提として、見ず知らずの武家屋敷の庭で「切腹させてくれ」、と申し出る貧しい侍たちが続出し始めた時代背景がある。
なんでそんなことが流行ってるのか?というと、ある大名が「貧して武士の名を汚すぐらいなら潔く腹かっさばいてその矜持を守ろうとする志たるや立派。誰かこのものに金品をもたせい!」ってやっちゃったから。
あ、切腹するふりをしたら金恵んでもらえるんだ!と貧乏浪人が色めき立っちゃったんですな。
次から次へとやってくるさもしい連中を追い払うのに、実際小銭を恵んでやる武家も出てきたりしたもんだから事態は収集がつかぬ有様となって。
物語はそんな状況下、名門井伊家を訪れる貧乏侍の姿で幕を開ける。
「庭先で切腹させてくれ」
「(またこいつもか・・・いい加減にしろよ、マジで)しばし待たれい」
井伊家家老登場。
「どうぞ」
「え?いまなんと?」
「切腹していただいてかまわん、と申し上げておる。まさか逃げ帰りはすまいな」
「・・・・(えらいことになった((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル)」
はい、もうこの時点でめちゃくちゃ面白いわけです。
史実として武家屋敷の庭先で切腹するなんてことが本当に流行ったのかどうかはわかりませんが、恥と体面を重んじる武家社会な世の中においていかにも起こり得そうな出来事だけに、創作だったとしてもその発想のもっともらしさに舌を巻かんばかり。
また同時に、ちょっと小銭を恵んでくれればよかったものを、本当に切腹させられる羽目になる貧乏侍の姿が階級社会の理不尽さ、非道ぶりをこれでもか、と浮き彫りにしていて。
そもそも天下泰平な徳川政権下において、武士なんざとうに無用の産物であって。
有事の兵隊を食わせておく余裕なんざ、幕府にはないわけだ。
そんな社会構造の歪みが、貧乏侍の脇差しが竹光であった、という事実で如実に語られていたりもする。
切腹したくとも出来ない惨めさを貧乏侍は武家屋敷で暴かれることとなるんです。
さて、家老はそんな竹光侍に何を命じたか?
なんだかもう南條範夫や平田弘史の残酷ものにも似て地獄絵図だったりするんですが、この映画がさらに回転数上げて加速してくるのはその後、貧乏侍の知り合いと思しき人物、半四郎が再び井伊家を訪れて「庭先で切腹させてくれ」と申し出てから。
え、なんなのこれ?なにが起こってるの?これ?と井伊家家老と一緒になって混乱する私。
そこからの展開はまさに怒涛の一言です。
何よりすごかったのは、庭先に座らされ井伊家配下の侍共に囲まれた状況で、半四郎が家老と問答を始めること。
いつ全員に襲いかかられるかわかったもんじゃない緊迫した状況下で、訥々と半四郎は家老の欺瞞を追求していくんですな。
なんでこんな命がけのディベートやってるんだよ!と手のひらは汗でじっとり。
今で言うところの検事と弁護士の丁々発止なやり取りにも似て、少しづつ明らかになっていく真相と半四郎の真の目的。
12人の怒れる男(1954)を思い出させるような、ミステリっぽいスリルすらあるんだからただ事じゃない。
この手の会話劇を時代劇という舞台でやるという大胆さにも恐れ入りましたね。
だってみんなチャンバラ期待すると思うんですよ、それをあえて裏切って延々しゃべり倒すという暴挙をやらかしてるのに、それが退屈さに繋がらないってのが脱帽する他なし。
エンディング、はっきり言って救いがないです。
そりゃ、こうなっちゃうわなあ、と納得するほかないんですけど、それでも半四郎が最期にぶっ壊したものに、この作品のテーマが見事集約されていて。
問答無用の傑作ですね。
監督は黒澤明を意識したらしいですが、はっきり言って肩を並べるレベル。
一切の見劣りなし、と言っていいと思います。
そりゃカンヌで審査員賞も受賞するわ、と納得。
勧善懲悪に染まらぬやるせなさがあるというのに、きっちりエンターティメントに仕上がってる時代劇の金字塔。
仲代達矢と三國連太郎のバチバチな演技も熱い、必見の一作、いやマジで面白かった。