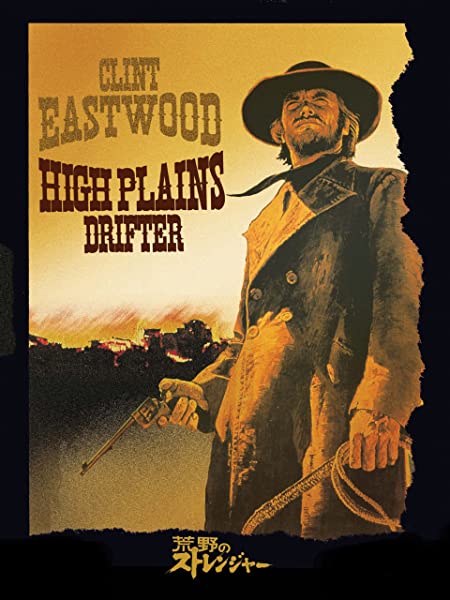イタリア 1954
監督 フェデリコ・フェリーニ
脚本 フェデリコ・フェリーニ、エンニオ・フライアーノ、トゥリオ・ピネッリ

粗暴で孤独な大道芸人の男と、その男に買われた薄弱の女の旅路を描いたフェリーニの最高傑作と名高い1作。
いわゆる「世の埒外に生きる人間たちの物語」と言っていいでしょうね。
主人公の大道芸人ザンパノ、怪力自慢だが人付き合いが下手で、酒飲んでしょちゅう暴れたり、小さな盗みを平気でやったりとか、昔はよく見かけた手合いの厄介者。
サーカス団に所属する機会を得ても、結局はメンバーと揉めて長続きしない。
組織に属せないタイプの人間です。
一方、薄弱の女ジェルソミーナは貧しさゆえ生家では持て余し気味。
で、わずかばかりの金でザンパノに売られてしまうんですが「ああっ、なんかもう手ひどい目にあわされちゃうのか?!」というと、実はそうでもない。
ザンパノは身の回りの世話をさせたり、大道芸の助手を務めさせるためにジェルソミーナをこき使うんですが、やがて少しづつ奇妙な共生関係が二人の間には成り立っていく。
愛だとか恋だとか、その手の安易な語り口でフェリーニは二人を描写しません。
かといって共依存とも違う。
言うなれば「望む形ではないかもしれないが、そこに居場所を得た」というのが一番正しいかもしれません。
これは私にとって、ある種小さな衝撃だったりもしました。
社会が成熟していくにつれて、弱者や障害者は人権を旗印に囲い込まれていくようになってきた、と私は思っているんですね。
体のいい言葉狩りや、平等を声高に叫んで「みんな同じ」に扱おうとする。
それが100%間違ってるとは言いませんが、両者間の「溝」に覆いをかぶせてなかったことにしても、足元の亀裂は消えたわけじゃないんで火種は永遠にくすぶったままです。
じゃあどうするのがいいのか?と考えた時、ザンパノとジェルソミーナのような関係性もありなんじゃないのか?と思えてしまいそうになるところがこの映画の怖さで。
それが正しいはずもないんですが、心の安息を得ることに方程式はない、としたこと自体が恐るべき慧眼であり、早すぎる問題提起だったように私は感じてます。
中盤以降の展開は涙なしには見れません。
ある事件をきっかけに、ザンパノはジェルソミーナと道行きを別にします。
愚かさをも含め、環境が整備されていなかった不幸もあるんですが、状況がザンパノのキャパを超えちゃった、ってのが正解でしょうね。
そのあとに迎えたエンディングのやりきれなさといったら、慟哭が空気を揺さぶるレベルの悲痛さだったと言っていいでしょう。
なにがザンパノには必要だったのか、ジェルソミーナとはなんだったのか、失われたもののささやかな輝きを、耳に馴染んだメロディにのせて演出するフェリーニの手管には感服するしかありません。
この作品を、登場人物の一人である軽業師がイエス・キリストそのものである、と解釈して「人の愚かさ、罪業を冷徹に切り取ったもの」と語る人もいますが、私の見立てではちょっと違う。
それだと冒頭に書いた「世の埒外に生きる人間たちの物語」であることが意味をなさないし、劇中のセリフである「世の中にあるものは全て何かの役に立っている。それがたとえ石ころだって」が単なる皮肉に聞こえてしまう。
普通に生きていくことがどうしてもままならない、他者と歩調を合わせることができない人間たちの心の平穏はどこにあるのか、さらには、もしザンパノがキリストを磔にし、脇腹を貫いた兵士だとするなら、彼自身の懺悔は誰が天に届けるというのか?つまりは救いとはどういうことなのか?というのが監督の問いかけであるような気がしますね。
文句なし傑作。
こんなものを54年に撮られた日にゃあ、後続はみんなやる気をなくす、と思った次第。