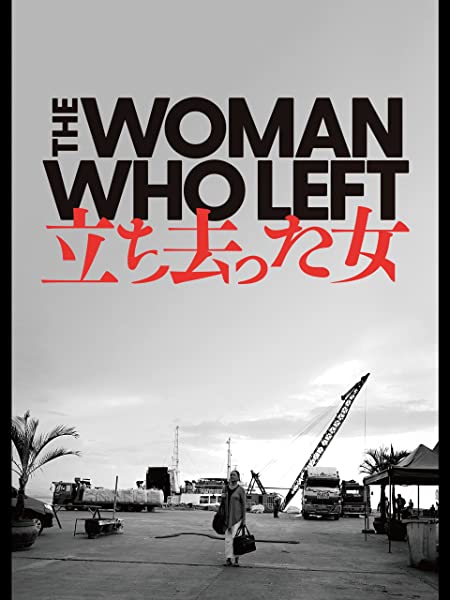アルゼンチン/スペイン 2016
監督 マリアノ・コーン、ガストン・ドゥプラット
脚本 アンドレス・ドゥプラット

ノーベル文学賞を受賞し、世界的な知名度を有する小説家が40年ぶりに帰った故郷の町にて巻き込まれる騒動を描いた作品。
コメディといえばコメディかもしれませんが、あまり笑わせようとしてないんで、どっちかといえば普通に人間ドラマでいいかもしれません。
テーマとなっているのは「故郷と言う名の村社会のおぞましさ」に他ならないですね。
そういう意味では先の展開にほぼ予想がつく。
名声を得た町出身の有名人が、捨て去った故郷に里帰りしたところでろくなことになりゃしない、ってのは、もうあえて検証するまでもなくわかりきった話であって。
最初の盛大な歓待が、徐々に悪意の対象と変わるストーリー進行は、ああやっぱりなあ、って感じでしたね。
また、主人公の作家、性格が悪いんです。
普段から本なんて全く読んでいないであろう無知無学な住人に、正面から芸術論、文化論をぶつけて町の催しを台無しにしたりする。
世間擦れしてないんですね。
適当に合わせておく、ってことが出来ない。
いかにもな専門バカ風。
それでいて下半身が幾分だらしない。
もめないわけがなくて。
数日だけ滞在してさっさと帰りゃいいのに、もう、ほんとにこの長っ尻が!と私なんかはやきもきしっぱなしだったりもしましたね。
予想外に秀逸だったのは終盤の展開。
コメディに若干よりかかる調子だった物語が、突然色を変えて凶悪なスリラーとでもいいたくなる怖さを見せつけてきます。
そこまで根深いものがあったのか、と私なんかは驚愕でしたね。
心の襞の奥底に沈む負の感情をみごと演出。
で、そのまま震え上がるようなオチに誘導してくれてたら私の評価は全く違ったんですが、エンディングがねー、ちょっと明後日の方向に行っちゃってて。
このオチだと「作家はネタのためなら虎穴だとわかっていても、あえて自ら飛び込まねばならない」という訓告めいたお話のようにもとれちゃうんですよね。
いや、それは物語の流れからして違うだろう、と。
妙な味わいがある作品であることは確かです。
そこは前作ル・コルビュジエの家(2009)にも通じる独自性があると思う。
でもこのエンディングじゃない。
悩ましい一作ですね。
各国の映画祭で高く評価されたのはわからなくもないんですけどね。