ドイツ 1919
監督 ロベルト・ウィーネ
脚本 ハンス・ヤノヴィッツ、カール・マイヤー
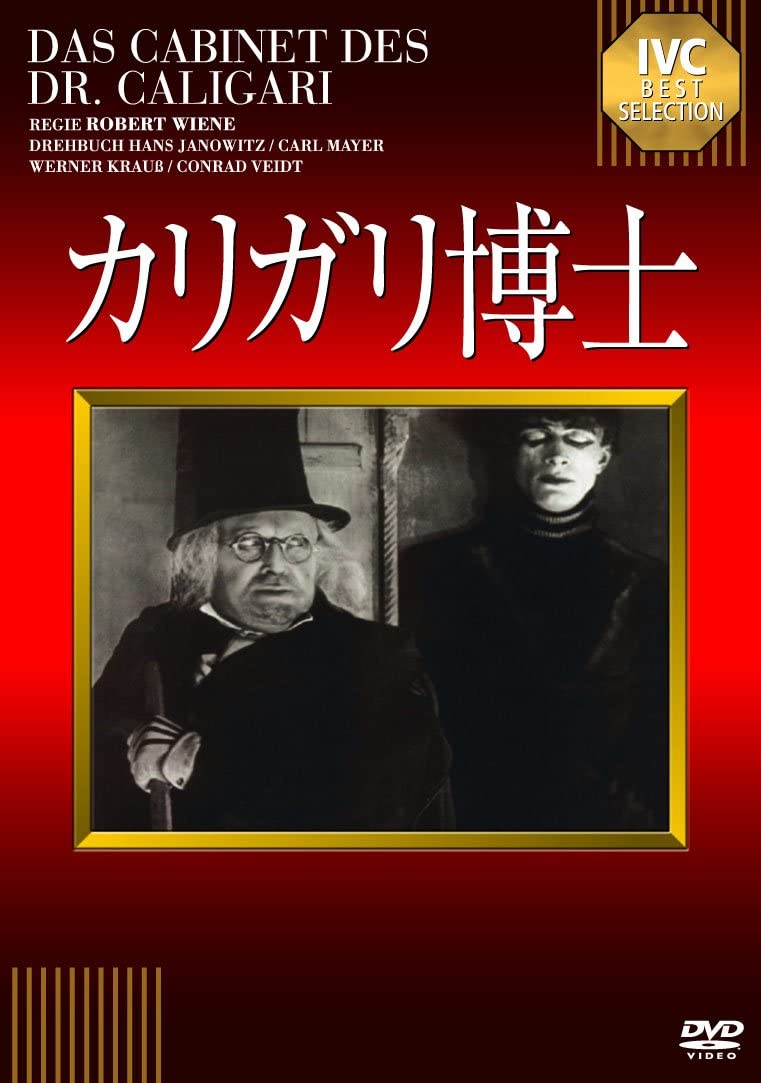
あらゆるホラー、スリラー映画の原点と言われる一作。
淀川長治氏の解説によると、ドイツ表現主義の代表的作品とのこと。
ドイツ表現主義ってのが私はよくわからないんですが「ヒトラーがドイツの先鋭的な文化を何もかも破壊してしまった」という口述から想像できるものはいくつかあったりはしますね。
ま、そこはお詳しい方にお任せするとして。
見てて私が強烈だな、と感じたのはなんといっても美術。
なにを思ったのか、町も家も風景もその全部が書き割りなんですよ、この作品。
どこの劇団の舞台なんだ、って話で。
特徴的なのは、書き割りのどれもが奇妙にデッサン狂ってて、方向性の見えてこないディフォルメで歪んでいること。
それでいてどこか絵画的な佇まいがあったりもする。
おもちゃのような家や街路を登場人物たちが行き来するんです。
なんなんだこのシュールさは?と唖然。
物語は、そんなどこともつかぬ町で起こった連続殺人事件を追う形で展開していくんですが、まあとにかく不穏でしたね。
今改めて見るとストーリーそのものはシンプルなんですけど、用意された素材がいちいちツボをついてて。
不気味な博士、眠り病に犯された美青年、予言を出し物とする見世物、精神病院等々、この手の映画を構成する重要な要素のあれこれがすでにこの時代にして出揃っているじゃないか、と。
凄かったのは、それを現実とも妄想ともつかぬエンディングで煙に巻いてしまったことでしょうね。
そりゃね、サイレントでモノクロですんでね、古さはあります。
スムーズにお話がつながっていかない、と感じた部分もあった。
けれど現代にまで連綿と続くホラー、スリラーのある種の「型」をね、先駆にして完全に完成させちゃってるんですよね、この作品は。
たった48分の映画ですが、原点と言われるだけのことはある、と納得。
現実感の乏しいハリボテな異郷で、狂気が交錯する様をアーティスティックに描出した傑作でしょうね。
古典、と侮れないものがありますよ、これは。

