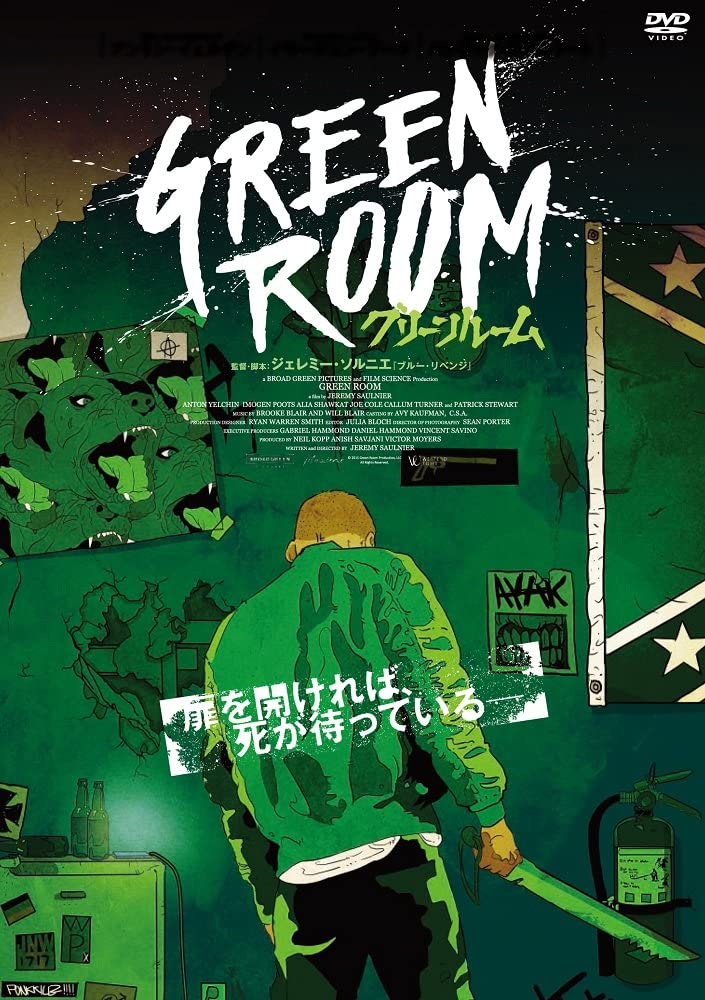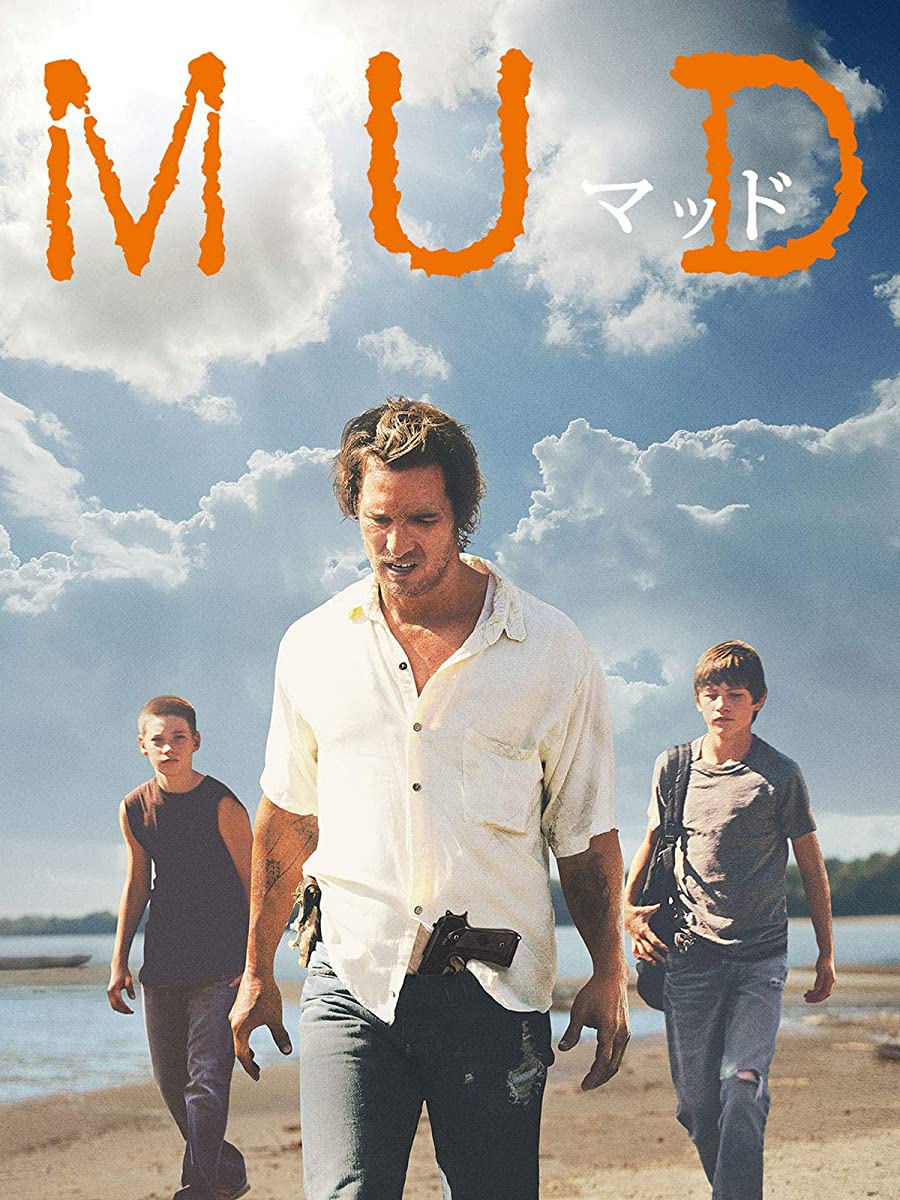アメリカ 2016
監督、脚本 マット・ロス

人里離れた山奥で、6人の子どもたちに文明を拒絶したサバイバルさながらの英才教育を施す変わり者のオヤジが、一家総出で町にやってきたことから巻き起こる騒動を描いた一作。
なぜ一家は突然、街にやってきたのか、それは母の葬儀のため。
双極性障害を患い、自死に至った母を、彼女の遺言に従って葬送してやるために教会に乗り込む、というのが物語前半の筋立て。
そこには娘を普通に土葬してやりたい、とする母の両親(祖父母)と、仏教徒である妻の遺言は違う、とする夫の対立があって。
祖父母は孫を学校にも通わせず、原始的な生活を強いている娘婿をひどく嫌ってるんですね。
それが娘の死によって表面化した、という構図。
さて、夫は妻の想いを汲んで遺体を奪還できるのか、そして子どもたちはどう行動するのか、が作品の見どころ。
全体のテーマとして掘り下げられているのは、教育とはどうあるべきか、という問いかけ。
これはしいては「生き方」にもつながる命題なのかもしれません。
ま、普通に考えて学校にも行かせず、鹿の仕留め方や、ナイフ一本でのサバイバル術、ロッククライミングの技術、ルーティンワークと化した激しい肉体の鍛錬で一日が暮れていく生活、ってやっぱり異常ですよね。
いや、最低学校には行かせるべきだろう、というのが一般的な考えだろうと思います。
私だってそう思う。
ところがこの自然主義な偏屈オヤジ、そう指摘されるのはわかってる、とばかりに学業に対する取り組みもおろそかにしてなくて。
夜はみっちりと子どもたちに勉強させることに余念がない。
これがまた恐ろしく知的水準の高い学び方で。
なんせ一番下の5歳か6歳ぐらいのお嬢ちゃんが、アメリカの権利章典を暗記していてすらすら諳んじられるばかりか、それに対する自分の考察まで述べられるほど。
単なる筋肉バカじゃないんですね。
さらにオヤジが凄いのは、子どもたちに対して決して高圧的ではないこと。
同じ目線に立って「反論があればちゃんと聞くし、それで自分が間違ってると思えば態度を改める」なんてことを言えてしまう人物なんですよ。
だから決して子どもたちは今の生活が嫌だとは思っていないんですね。
むしろオヤジになついていたりする。
そこまでを物語の流れから理解して、さて、これは本当におかしな教育なんだろうか?オヤジは間違ってるのだろうか?と見る側としては徐々に価値観がゆらいでくるわけです。
イジメがはびこり、ゲーム三昧で、コミュ障な子どもたちが増産される今の社会のあり方は正しいのだろうか?と。
ただ、オヤジの教育法にも盲点はあって。
それは家族以外の他者との交流が一切断絶されていること。
物語はその唯一の矛盾点を厳しく突いてきます。
とはいえ、オヤジが絶対悪であるとも言い切れないのは確か。
中盤以降の展開は、何が正しくて、何が間違ってるのか、ひどく考えさせられる内容でしたね。
祖父母もオヤジも正しい事を言ってる、故に答えが見つからない。
正直、肝心な後半の展開は、明確な着地点を提示する、というより、情に流されちゃった、みたいな感じではあったんですが「みんなが信じ込むあたりまえ」に投げ込まれた波紋は思いのほか大きかったように思います。
白眉はエンディング間近の、家族が岸辺につどうシーンでしょうね。
詳しくは書けないんですが、決まった形をなぞるのではなく、それぞれがそれぞれの思いを形にしたもので別に構わないのだ、とした自由さが多様性を感動的に演出していたように思います。
実に見ごたえのある一作でしたね。
ちょくちょくコメディ調のくすぐりを挿入してくるのもうまい。
子供が「コーラってなに?」と聞いて「毒の水だ」と即答するシーンには爆笑。
文明化のもたらしたもの、画一化、規格化がもたらしたものがなんであったのか、物語の語りかけるものは相克して豊穣です。
私は好きですね、この映画。