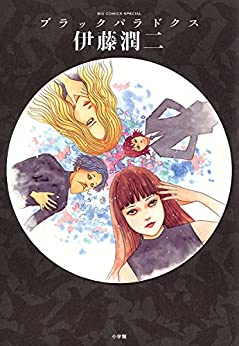アルゼンチン 2015
監督 パブロ・トラペロ
脚本 パブロ・トラペロ、フリアン・ロヨラ

軍事政権が崩壊し、民主化へと移行しつつある1980年代のアルゼンチンを舞台に、軍の要職にあった父親とその一家の「変化に取り残された日常」を描いた一作。
なんといってもこの物語が実話を元にしている、というのが驚きでしたね。
というのも父親、新しい政権が誕生し、当時の軍部はほぼ解体に追い込まれているというのに「新政権は決して長持ちしない」と信じ込み、大佐と呼ばれる謎の人物の命をうけて富裕層の子供を誘拐し身代金をせしめる悪事に手を染めているんですよ。
それが政争にどんな影響をもたらすのかはよくわかりません。
しかし父親、一片の迷いもなく下された命令を次々と遂行。
で、問題なのは誘拐した子供をどこに監禁するのか?なんですが、なんと父親、自宅に連れかえってくるんです。
そう、家族ぐるみの犯行なんですね。
主犯は父親なんですが、協力者として長男と次男、三男、母親は事実を知りながらも見て見ぬふり、幼い妹はよくわかってない感じ。
時には長男の友達すらターゲットとなり、長男は友人をおびき出すために協力を余儀なくされたりする。
クローズアップされているのは絶対的な父権。
それが悪いことであると知りながらも家族の誰一人として父親には逆らうことが出来ない。
で、父親、対外的には紳士でいいお父さんだったりするんです。
必然的に家族は外面と裏の顔を使い分ける二重生活を強いられる羽目になる。
やりたくないけど、やらざるを得ない長男の葛藤を描いた前半は、待ち受ける破滅を匂わせながらもかなり見応えがありました。
言うなればこれ、父親の影響下からどう抜け出して1人の男として自立するか、を描いた物語でもあるわけです。
ただ、事が事だけに、もうやめた、後は知らない、と割り切ることができない難しさが当然そこにはあるわけで。
自分一人が知らぬ存ぜぬを決め込んだところで、残った家族で犯行は続いていくわけですから。
はたして長男はいつ終わるとも知れぬ悪夢にどう終止符を打つのか、シナリオ展開に予断を許さぬものがあったことは確か。
物語が大きく動き出すのは終盤。
あるきっかけで、長男は初めて父親の命令に背くんですね。
そこからの展開は怒涛。
予想通り、破局は唐突にやってくるんですが、やはり絶句もので衝撃的だったのはラストシーンでしょうね。
ああ、もうそれしかなかったのか長男よ、と。
もっと早い段階で何か対策をうてたんじゃないか、とその愚かしさを糾弾したくなったりもしたんですが、じゃあなにをすればよかったんだ、と問われて明確な答えが返せない自分が居たりもする。
家族という極小の単位にひそむ狂信的価値観に焦点を当てた秀作だと思います。
アルゼンチンだから、時代の変革期にあったから、ってことじゃない。
世界中、どの家族であっても似たようなことは十分起こりうる。
他者の介在、社交性って実は過ちをギリギリで回避する大事なメソッドなのかもしれないなあ、とふと思いました。
ま、それすらも救いになりそうになかったことに、この物語のやるせなさがあるわけですが。
事実が創作を凌駕って、こういう物語のことを言うのだと思います。
嫌な後味が強く記憶に残る力作でしたね。