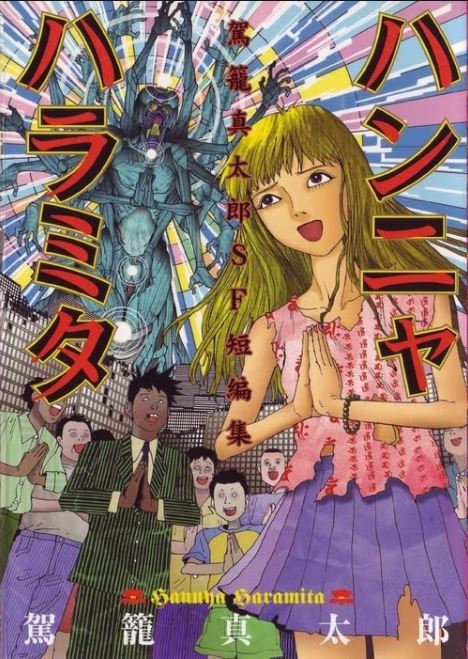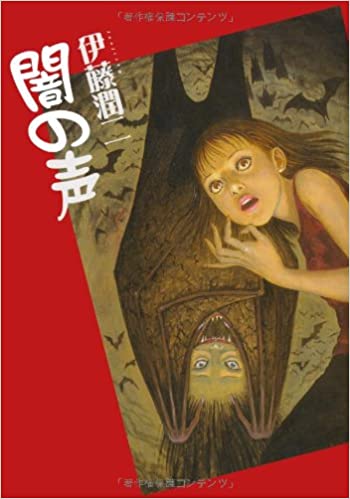アメリカ/イタリア/メキシコ 2016
監督 マーティン・スコセッシ
原作 遠藤周作

江戸時代の長崎を舞台に、弾圧される隠れキリシタンを描いた作品。
思ってたよりずっと面白かったし、162分という長丁場の割にはダレなかったことは評価に値するように思います。
やっぱりこの作品ってね、来日した外国人宣教師の目線で綴られてますんで、宗教映画のくくりからは逃れられないように思うんで。
信仰を貫くとはどういうことなのか、という問いかけがその根源にはありますし。
普通はそこに「とっつきにくさ」を感じそうなものだと思うんですよね、正月とクリスマスが同居してて平気な日本人の宗教観からするなら。
なのにさほど奇異な印象を受けることなく最後まで見れてしまう。
何故か。
それはこの物語の構造が「権力者VS自由を求める少数の弱者」になってるから、に他なりません。
これって、わざわざ例を持ち出すまでもなく、エンターティメントの鉄板とも言える図式だと思うんですね。
「巨悪にたった一人で挑む徒手空拳の男」とか「ファシズムに屈せず戦い抜いた1人の自由主義者」とか、その手のキャッチコピーが踊る作品に心惹かれた経験は映画好きなら誰しもがあるはず。
キリスト教云々以前に、弾圧者たる長崎奉行に主人公である宣教師ロドリゴはどう抗していくのか?が巧みに観客の心を捉える仕組みになってる。
つい応援したくなってしまうわけですよ、非道な仕打ちに負けるな、ロドリゴ、と。
それはいつしか彼の信じるイエスの教えが、宗教を超えて「揺るがぬ鋼鉄の信念の具象化」であるかのような錯覚を起こさせるほど。
そこに無宗教者すら熱くなってしまう反骨のヒロイズムがあったことは確か。
ただね、私はこれを額面どおり受け取っちゃうのはちょっと危険だな、と思ったりもするんです。
この作品を見て勇気をもらったとか、感動した、とか言う人をくさすつもりはないんですが、物語の前提として「なぜ日本はキリスト教を敵対視し、根絶しようとしたのか」ということに関する描写がこの作品からはすっぽり抜け落ちゃってるのが私は気になるんですよね。
キリスト教を世界に布教しようとする背景には、諸外国の植民地政策があるわけです。
そりゃ末端の宣教師にそんな自覚はないかもしれませんよ、でも彼らがはからずもアジア侵略の尖兵となっていたことは歴史上の事実。
実際、滅茶苦茶やってるわけですよ、当時の宣教師は。
寺社仏閣を信徒に焼き討ちさせたり、異教徒を人間扱いしなかったり。
豊臣秀吉との話し合いにもイエズス会は応じなかったらしいですから。
作中では「日本という沼にはキリスト教は根付かない」とか言ってますけど、それ以前に禁じられるだけの所業をやらかしたから武力で抑え込まれる羽目になった、という経緯がちゃんと存在してるわけです。
そこをスルーして一方的な被害者顔されてもですね、信仰の自由や教えの尊さを解くことには繋がらないですよね。
終盤の展開も少し疑問。
教えに従うなら宣教師は殉教すべきなんじゃないのか?と思うんですが、さんざんごねたおして何人も見殺しにしておきながら、最後の最後で結局あの選択かよ、と。
でも実は心の奥底に信心はずっとあったんです、って、なんだそれ?と。
その処世術の狡猾さをもっと早く信徒に教えてやれよ、って話であって。
人間ドラマとして見るなら、歴史に翻弄され数奇な運命をたどる男を描いた実に見ごたえのある大作だと思いますが、宗教的側面から推し量るならファンダメンタリストにとって都合のいいお涙頂戴と思わなくもありません。
ややこしい映画、の一言ですね。
江戸時代の日本を外国人が描いたとは思えぬほど違和感なく再現してみせたセットや、イッセー尾形の怪演、塚本晋也の熱演等、見どころはたくさんあると思うんですが、これをオススメと素直に言っていいのか、悩むところ。
抑圧された人間がなにを宗教に求めるのかを見せつけられたのは興味深かったですが。
ちなみに、結局キチジローとはなんだったのか?というのが唯一読み解けなかったんですが、まあ、いいか。
巨匠の名に恥じぬ質の高さは老いてなお堅持してる、とは思いました。