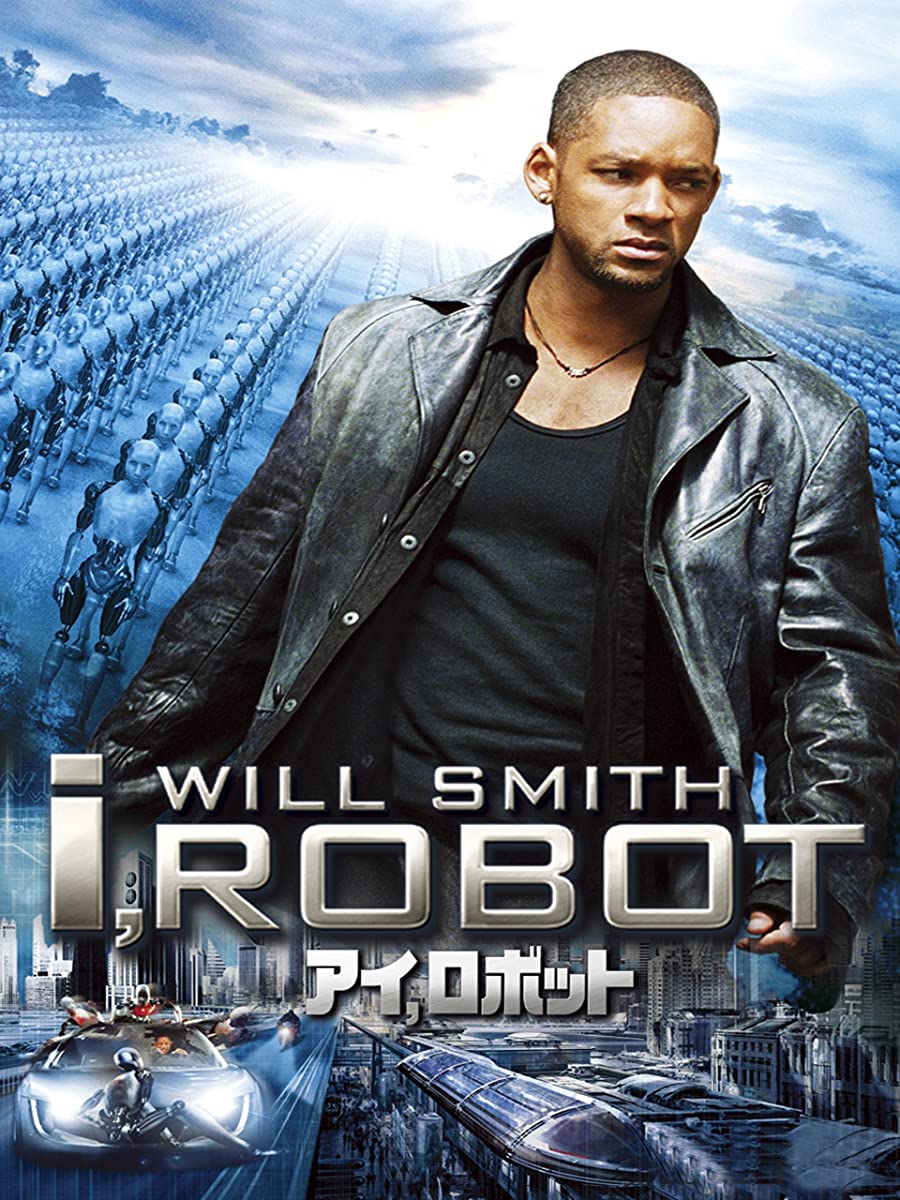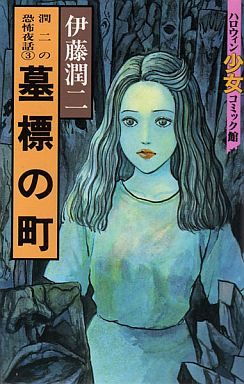アルゼンチン 2009
監督 ガストン・ドゥプラット&マリアノ・コーン
脚本 アンドレス・ドゥプラット

外国に限った話じゃない、日本でもおなじみな隣人トラブルを題材にした作品。
タイトルになっているル・コルビュジエってのは建築家の名前で近代建築の3大巨匠と呼ばれた人物。
主にフランスで活躍した方らしいです。
物語の舞台はそのル・コルビュジエが南アメリカに唯一建てた私邸、クルチェット邸。
これ実在する建物だとか。
そこに住む椅子デザイナーである主人公が、ある日、自宅側に向いた隣家の壁に大穴が開けられているのを発見するんですね。
隣人はそこに窓を作る、と言う。
主人公、慌てます。
そんなところに窓を作られたら邸内が丸見えになる、と。
その改築は法的にも認められていない、と主人公は力説するんですが、それが根拠のあるものなのかどうかははっきりしません。
ブラフっぽい感触もなきにしもあらず。
隣人は覗き目的じゃない、バカにするな、採光窓として必要なだけなんだ、と力説。
両者一歩も譲らない。
また、この隣人がなかなか曲者なんです。
そこまで言うなら窓は塞ぐ、と一旦は言いながら、それを一向に行動に移す気配がない。
ラテン気質というか、馬の耳に念仏というか。
何を考えているのかよくわからないところのある人物で、どっちかというと変わり者。
さて、主人公はどうこの問題に決着をつけるのか?が大筋のストーリーラインなんですが、私が見ててうまいな、と思ったのはどちらに絶対的な否があるのか、容易に判断できない問題提示の巧妙さでしたね。
自分ちに窓を作って何が悪い、という隣人の主張もわからなくないし、覗く気がないにせよプライバシーの侵害にあたる、という主人公の主張も筋が通ってるように思える。
そこで活きてくるのが、この家はル・コルビュジエの家なんだぞ、という舞台設定で。
やっぱりね、他所から今でも見学者が来るような希少な建築物なんだから、景観を鑑みるなら自分の権利ばっかり主張するのも良くないかも、という考え方もあると思うんです。
至極日本人的な感覚なのかもしれませんけどね。
で、そんな穏便を良しとする協調意識を後押しするのが、隣人の我の強いキャラクターで。
どっちが正しいと確信を持てたわけじゃないのに、だんだん隣人が悪いんじゃないのか?といつの間にか印象操作されてしまうドラマ作りのうまさがあるんですよね。
このミスリードの手口はなかなかのテクニックだったと思います。
もしこの作品がスリラーなら、間違いなく隣人は地下室に死体を隠してるな・・なんて私は思ったぐらいでしたし。
それがエンディングにおける予想外の結末に見事反映された、とも言えるでしょう。
最後の最後に観客は気づかされます。
ああ、この物語はトラブルの是非を問うものでなく、エゴを描いた作品だったのだと。
終わってみて、そういえば主人公は主人公で結構嫌なやつだった、と私なんかは改めて気づいたぐらいで。
まんまとのせられてる、とはこのことでしょうね。
どちらかといえば小品かとは思いますが、純然たる善意すらエゴの前では色褪せる、としたラストシーンはなかなか強烈だったように思います。
あんまり後味の良くない作品ですが、ある種の人間の本質を描いてる、そんな風にも思った一作でした。