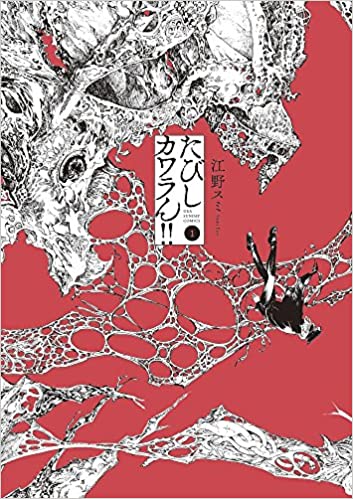アメリカ 2014
監督、脚本 ディミアン・チャゼル

なんとも凄まじい。
まばたきする暇もなく怒涛の107分。
久しぶりに強烈な作品を見た気がします。
スポ根丸出しの音楽大学の教授と、その指導に食らいつこうとする生徒の姿を描いた作品なんですが、これがもう常軌を逸して熱い。
星飛雄馬どころの話じゃないです。
なんせ双方にまるで信頼関係がないんです。
生徒であるニーマンは認めてもらえることでしか突破口をみいだせず、かたや、教授のフレッチャーはどうすればジャズの世界に天才を生み出すことができるのかしか頭にない。
誰が言ったか知りませんが格闘技映画とはよく言った。
倒すか、倒されるか。
カタルシスを見出すとしたらその1点。
卓越した技術を習得する、ということはここまで狂気をともなうものなのか、と知らしめただけでもうこの作品は半ば成功しているように私は思います。
さらに私が感心したのは、ジャズを極めたところで安定した生活が待っているわけではない、と作中で言及している部分。
つまり、口に糊するのに格別役立つわけではないとわかっていながら、すべてを棄てて音楽に取り組むバカさ加減をこの作品は否定していないんですね。
描かれているのは音楽という名の「魔」です。
軍隊かよ、とつっこみそうになるフレッチャーの指導法も、それに抗いつつも音楽を棄てられないニーマンもすべては音楽に取り憑かれたプレイヤーという名のジャンキーの姿、そのもの。
そして、強烈に嫌なエンディング。
ここで監督はフレッチャーの人間性みたいなものをあからさまにします。
最初から大嫌いだったけど、心底嫌いになった、と私なんかは憤慨するわけですが、善悪やモラルすら超えて両者の橋渡しをしたものが最後の最後に狂い咲くように描写されてて圧巻。
つくづく「表現する」ということはすべてを超えて業が深い、と思わされました。
ジャズ、ということで敬遠する人もいるかと思いますが、門外漢でも充分楽しめる一作だと思います。
熱量が半端じゃない。
あっけにとられる傑作。
余談ですが、 作中でフレッチャーがニーマンのドラミングを「早い!」「今度は遅い!」と、そのテンポについて罵倒しまくるシーン、私、どこが走ってて、どこがもたってるのか、全くわかりませんでした。
実際に誰がプレイしているのかわかりませんが、そこまで正確にやってるのか、それとも私の耳がダメなのか、凄く気になった。
やはり「無能はロックをやれ」と作中で揶揄されたロック畑でプレイし続けたような人間では、その真贋は見極められんのか。
あえて負け惜しみを言うなら、天才は最初から天才なんだよ、フレッチャーよ、ってなところでしょうか。
ニーマンがよく聞いてたバディ・リッチなんて楽譜も読めなかったのに11歳でバンドリーダーをつとめ、後世に名を残してますし。
ああいかん、なまじっか音楽をかじってるとひどく心惑わされて、余計なことを書いてしまう。
とりあえずなんかもう脇の下、汗じっとりでしたね、私。