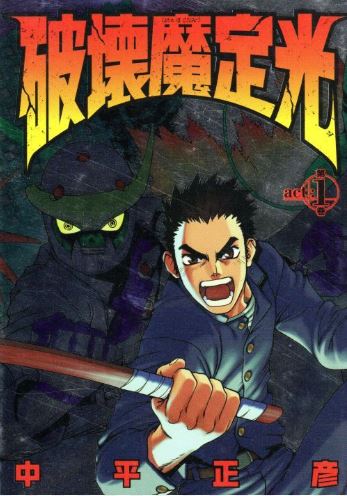アメリカ 1991
監督 テリー・ギリアム
脚本 リチャード・ラグラヴゥネーズ

不用意に放った一言が、間接的に殺人事件に発展してしまった不遇なラジオのDJの贖罪と再生を描いた物語。
これまでのギリアムの監督作の中では初めての現代劇で(モンティパイソンは別にして)、あれ?不思議の世界に行ったり、ダクトが部屋中にのさばったりしないの?と当時若かった私はとても戸惑ったのを記憶しています。
まあ、それなりにファンタジックではあるんですが。
なにがこれまでと違うか?って、ギリアムお得意の二挺拳銃「毒」と「笑い」が薄味なんですね。
笑いに関してはロビン・ウィリアムズのタガのはずれた一人芝居や、オカマのホームレスが一手に担ってはいるんですが、どこかアメリカ的、というか。
過去のギリアムのアイロニカルな笑いと若干質が違うように私は感じました。
なんといいますか、作品の色合いがすごく生真面目なんですね。
生真面目さすらせせら笑い、 シニカルに混沌な展開で撹乱する手法こそが監督の醍醐味かと思うんですが、それがどこか影を潜めてるんです。
至極真っ当にドラマチックさを追求しようとする作品作りは往年のファンにとって物足りないもの、に映るかもしれません。
結局ジェフ・ブリッジスとロビン・ウィリアムズ、その2枚看板の映画なのかもしれません。
主人公にとっての贖罪とは、なんだったのか、それをもう少し明確に描けていたら、らしくない作品とは言えど別の側面からの評価も可能だったんですが、なんとなく立場を違えた友情ものに着地してしまったあたりが個人的には減点。
ただこの作品のジェフが、彼の出演作の中でなぜだか私は一番好きですね。
それが収穫ですかね。