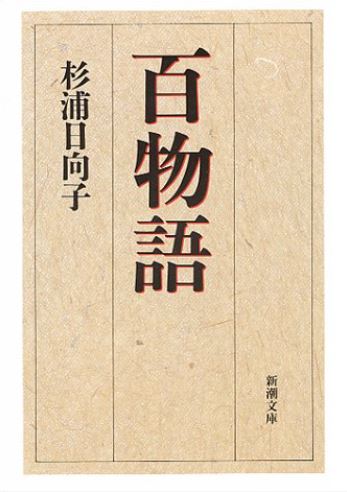1983年初版 杉浦日向子
ちくま文庫
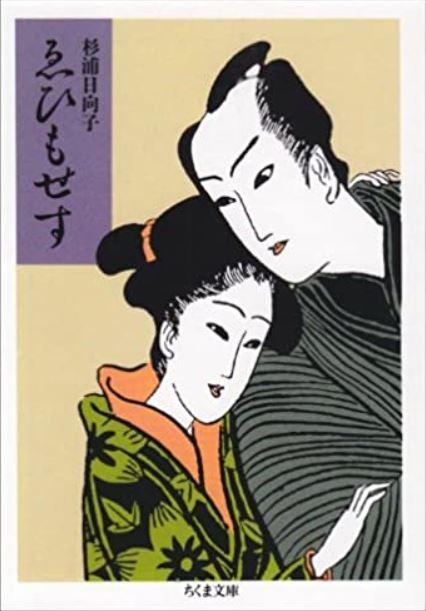
<収録短編>
袖もぎ様
ぼうずのざんげ
もず
通言室乃梅
ヤ・ク・ソ・ク
日々悠々
花景色狐巷談
崖
駆け抜ける
吉良供養
デビュー作「通言室乃梅」を含む短編集。
80年代当時はやまだ紫、近藤ようこと並んでガロ三人娘と呼ばれていたようですが、私の感触では一番世界(江戸文化)を深掘りしてるし、誰も見向きもしなかったところに目線を合わせた漫画家だと思いますね。
普通時代劇というとチャンバラの要素は必須かと思うんですが、作者の漫画には血なまぐさく即物的な命のやり取りとか、ほとんどでてこない。
そんなことより当時に生きる人達のさりげない日常であったりとか、色街に暮らす女の怯懦な心模様に焦点が当てられていたりする。
少なくとも漫画の世界では、杉浦日向子以前にこういう形の時代漫画を描いた人は居なかったように思います(あ、一ノ関圭がいたか)。
また当時の文化や言葉遣いに関する知見が半端じゃなくて。
時代劇は好きであれこれ読み漁っていたつもりでいたんですが、いかにこれまでの時代劇が現代的にわかりやすく翻案されたものであるか、思い知りましたね。
意味がよくわかんないセリフとかあるんですから。
これ、古語じゃねえのか?(違う)みたいな。
文芸漫画とはよく言ったものだと思います。
こんなの時代劇作家の一部の古い小説でしかお目にかかったことない。
ガロはすごい拾い物をしたなあ、と思いますし、またガロにしか発表の場がなかった、というのが怖い話だと思いますね。
ネットが発達してない時代ですから、そのまま在野に埋もれてしまった可能性だってあったわけですし。
漫画家としてのテクニックはまだまだだな、と感じる部分もあるんですけど、本当に好きで向学心を併せ持って持ってないと描けない作品群だと思いますし、拙いながらもすでに独特のペーソスと小さなユーモアがあるのがいい。
100%現代の商業誌では通用しない作風だと思いますが、こういう漫画を素通りしていっちゃあ駄目だと思いますね。
失われた時代を描写する、ってこういうことなんだと思います。