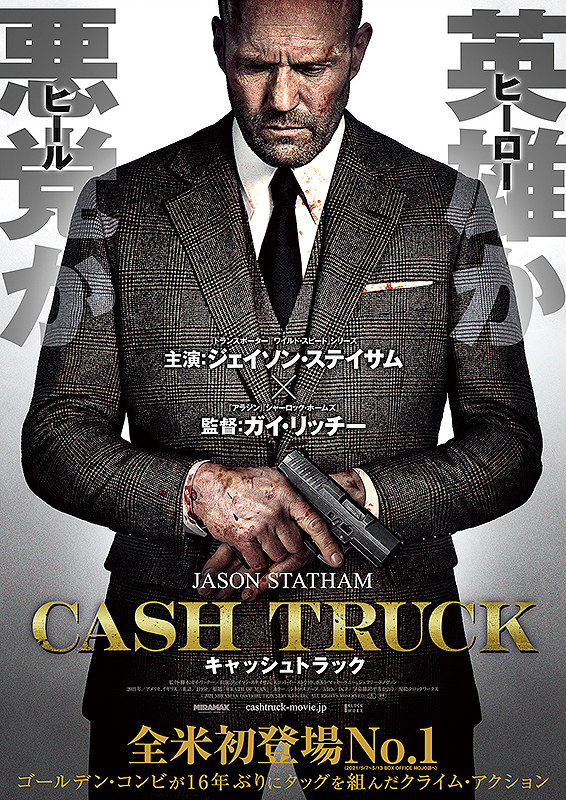2016年初出 白井カイウ/出水ぽすか
集英社ジャンプコミックス 全20巻

12歳になると、必ず出ていかねばならない孤児院が、実は食用人間の飼育場だった、という設定はあえてパクリだ剽窃だと騒ぐほどのこともなく、昔から似たようなプロットがあったと思うんですね。
はっきりと覚えてないですけど、すでに70年代にはそういう短編小説書いてた作家が何人かいた気がするし、人間農場みたいなネタは映画でも流用されて来たように思います。
なのでむしろ、その手の古い題材であえて勝負してきた、と見るほうが正しいように思うんです。
手垢の付いたネタを、どう新しい切り口で読ませてくれるのか?と。
とりあえず、序盤における、施設のママと子どもたちのギリギリの頭脳戦、際どい駆け引きはよくできてたと思いますね。
古い話で恐縮なんですけどスティーブ・マックィーンの大脱走(1963)を思い出したり。
プリズン・ブレイク(2005~)もそうでしたけど、この手の脱獄ものってある意味鉄板ですからね。
よほどの下手を打たない限り、間違いなく盛り上がる。
ましてや本作における脱走者は施設における子どもたち全員(全員12歳以下で数十人に及ぶ)。
スタローンやシュワルツェネッガーが味方にいたって到底無理、ってな話だ。
さて、子どもたちは一体どのようにして不可能を可能にするのか?これが読んでて面白くないわけがない。
で、この漫画がすごかったのは、安定して読者を逃さないであろう脱獄もの的な展開をさっさと4巻ぐらいで終わらせて、孤児院の外に広がる世界を舞台に物語を綴り始めたこと。
うわ、本気でファンタジーをやろうとしてる、と私はちょっと驚いた。
人間の捕食者である「鬼」がいる世界、ってことだけしか読者には情報が与えられてないんですよ。
つまり、全部新たに脱獄後の世界を構築していかなきゃならない。
しかも主人公のエマは「世界を変えてみせる」とか宣ってる。
せっかく孤児院脱獄編が面白かったのに、なんという難事業に手をだすのか、作者は、と。
捕食者がいる世界で主人公たちが生き抜いていくアクションファンタジーなんて、それこそ世の中には星の数ほど存在してるわけですから。
なにか一つ間違えたら即アウトなレベルで綱渡りなのは間違いない。
うわー、こりゃ駄目かもなあ、と正直テンション下がってたんです。
ところがだ。
わかりやすい手口が鼻につくものの、これが意外と飽きさせない。
とかく緻密なんですね。
ストーリーに一切の破綻や矛盾がない。
既視感すらも手玉に取って、丁寧に仕掛けを回収していく構成力にも感心させられた。
特にノーマンが再登場するシーン、これは見事!と膝をたたきましたね。
前フリがあったんでいつかは出てくるんだろうな、と思ってたんですが、まさかこの場面で登場するとは・・・と舌を巻く。
もうね、とんでもない風呂敷を広げてるんですよ。
でもこの調子なら広げた風呂敷も慌ててたたまずにすむのでは・・・と思えてくるほどにシナリオ進行、物語設計に無理がない。
で、最も素晴らしかったのは、子供故の純真さから、ひたすら甘っちょろい事を言い続けるエマの真っ直ぐな心、博愛主義的な生き方を歪めることなく最後まで完遂させたこと、でしょうね。
読んでてとにかくイライラするんですけど、いざ終わってみれば、中途半端なニヒリズムや屈折に支配された昨今の暗い漫画より、ずっと正しく少年漫画なのでは?と思ったり。
偶然うまくいっただけな部分ももちろんあるんですよ、でもそれすらも含めて「信じ続けることの大事さ」を強く印象付けてくるんですよね。
エンディングのひっくり返し方も上手。
絶対なにかあるだろうな、とは読者みんな考えてたと思うんですけど、ペシミスティックにビターエンドな顛末ですら子どもたちは持ち前の行動力とエマから教わった諦めない心で乗り越えていく。
もう一度、世界を信じてみたくなるシリーズでしたね。
ファンタジーとして特別なことは特にやってないんですけど、丁寧に考え抜かれたシナリオが既出作を軽々と越えていった、と言っていいでしょう。
傑作。
ここ数年で最も優れた原作者と言っていいと思いますね、白井カイウ。
ジャンプというよりサンデーっぽい内容だなあ、と思ったりもしたんですが、こういう漫画をも懐の内に取り込みだしたんだとしたら恐ろしいことになるぞ、少年ジャンプ。
余談だがイザベラには泣いた。
今回は泣くようなことはないだろう、と思ってたんだけど、またしてやられて近年のジャンプの凄さには悔しさを覚えん限りだ。